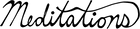NEW ARRIVALS
1372 products


1980年代初頭のパンクバンドThe Freezeから発展した、スコットランド出身のアーティスト、CinderによるソロプロジェクトCindytalkによる90年代インダストリアル、エクスペリメンタル・ロックの隠れた名盤。1994年にリリースされた当時から「スコットランド独立への呼びかけ」として構想され、過去から現在に続く独立への衝動を音で掬い上げながら、ポストパンク、インダストリアルの文脈の中で唯一無二の存在感を放ってきた作品。アルバムは、イギリスのフォークソング「The First Time Ever (I Saw Your Face)」をボーカルソロで痛々しく歌い上げる形で始まり、その後、Cindytalkの代表曲「A Song Of Changes」へと続く。そこからは、熱狂的な悲歌、思索的なスピリチュアル、ノワール的な抽象性、グラスゴー出身の作家Alasdair Grayが参加したスポークンワーズ、バグパイプのドローン、終末的なポストパンクなど、様々なスタイルが不規則に展開。This Mortal Coilとの接点から、90年代のハードコア・テクノ、さらにはMegoでの電子作品群へと繋がるCindytalkの活動史の中でも、不安定で困難な環境のもと制作された『Wappinschaw』は、最も闘争心と祈りが濃縮された瞬間を刻んでいる。


アフロ・コロンビア音楽新世代を世界に知らしめたシステマ・ソラールの中核メンバーによるプロジェクト、エル・レオパルドの2ndがリリース!カリブ海のパーカッション、アナログ・シンセ、ディープ・ベース、エレクトリック・ギター、そして彼のトレードマークとも言えるコロンビアの伝統的フルートであるクイシ、トランペットの催眠術のようなバイブレーションによって無限の宇宙を永遠に漂っているような気分にさせてくれるとんでもない内容!1970年代から80年代にかけてのカリブ海のトロピカル・サイケデリアへのオマージュとテリー・ライリーやクラフトワーク、マッド・プロフェッサーからの影響が結びつく独自のサウンド!


約2年振りとなるKendra Morris待望の最新作『Next』。Colemine Records の Leroi Conroy との共同プロデュースのもと、オハイオ州ラブランドのスタジオでヴィンテージ機材を駆使して録音。Tascam 388 を通した音像は、ツヤや洗練よりもざらつきや手触りを優先し、温かみのあるアナログ質感を全編にまとわせている。ゲストには Delvon Lamarr Organ Trio の Jimmy James、The Black Keys 周辺で知られる Ray Jacildo が参加。作品全体はどこかローファイなコンセプト・アルバムのような趣きがあり、ジャケットにある古いボードゲームやレトロなテレビ番組に通じるDIY感覚を下敷きにしているよう。音楽的には、ドゥーワップやブームバップ、ロックステディといった異なる要素を縫い合わせるように展開し、まるでニューヨークの古き良き記憶をコラージュしたような世界を描き出す。洗練よりも遊び心や想像力を優先するように、完璧さとは無縁で、むしろその不完全さの中にこそ息づくハートとイマジネーションが詰まったアルバム。カラフルでいてどこか懐かしいサウンドに、心に響くソウルフルな歌声が溶け合う一枚。

オリジナルは1973年に〈Bacillus〉からリリースされたセカンド・アルバム。前作のヴォーカル主体のプログレ・ロック路線から大きく舵を切り、ジャズ、エスニック、アシッド・ロックを自在に混ぜ合わせたサウンドへと進化した作品で、メンバーも刷新され、マルチインストゥルメンタリストの Eddy Marron、ベースの名手で創設メンバーの Reinhard Karwatky、そして超絶技巧のドラマー Peter Giger のトリオ編成になっている。盤全体に漂うスペーシーな即興感覚、エスニックな音色の実験、そして強烈なジャズ・フィーリングが渦巻いており、ロックでもジャズでもないはざまの領域に立ち、独自の美学を築いた作品。ドイツ産ロック史の中でも屈指の異色盤として知られる、技巧派トリオが織りなす異世界ジャズ・ロックの名品。

オリジナルはAlvin “GG” Ranglin のレーベルから1981年にリリースされた、グレゴリー・アイザックスの代表的コンピレーション第2弾。全10トラックで、彼特有のスムースでメローなルーツ・レゲエを存分に味わえる内容になっている。「Border」や「Village Of The Under Priviledge」、「Tumbling Tears」など、都会の影や弱者の視点を繊細に描く歌詞と、Isaacs の甘くしっとりとしたヴォーカルが印象的で、バックのリディムはあくまで落ち着きのあるルーツ寄りで、夜の静かな時間にぴったりの温度感。甘くしなやかな声で都会の影を歌う、ルーツ・レゲエの名手グレゴリー・アイザックスの極上メロウ集!

80年代初頭、ジャマイカのルーツ、ダンスホール・シーンで頭角を現した Delton Screechie による82年作極上ルーツ・アルバムの公式再発盤。録音は Harry J’s スタジオでミリタント・リズムをバックに行われ、その後キング・タビーのスタジオでヴォーカルとミックスが施されている。タイトル通り、アルバム全体を通して社会的メッセージや都市の苦境を歌うルーツ歌詞が中心で、Screechie の表現力豊かな声が、硬質で骨太なリディムと絡み合う。タフなリズムに支えられたそのいなたい歌声は、初期80年代ジャマイカン・ルーツの熱気を封じ込めた名盤。

ジャマイカン・ルーツ、ダブの深淵を掘り下げるリイシュー、Tafari All Stars の『Rarities from the Vault Vol.2』は、〈Wackies〉、〈Aires〉、〈Earth〉などの初期レーベルからのレアトラックやダブプレートを集めた掘り出し物集。注目は、Leroy Sibbles と Stranger Cole をフィーチャーしたダブプレート群。Sibbles は Studio One 時代の自身の「Guiding Star」リズムを Bullwackies でリワークして提供しており、ファンにはたまらない逸品。また、冒頭のトラックでは、Little Roy と共に Glen Brown の「Wedden Skank」を大胆に乗っ取る演奏も収録。全体を通して、粗削りで土臭いダブのエッセンスがぎっしり詰まったアルバムで、単なる過去音源の寄せ集めではなく、当時のサウンドシステム文化やレコーディング現場の空気感まで感じさせる、まさに掘る楽しみのための一枚。

オリジナルは1979年リリースの、ジャマイカのルーツDJシーンを代表する一人、Prince Hammer による重要作。バックを固めるのは Channel One の最強リズム隊 The Revolutionaries。さらに Prince Jammy、Errol Thompson、Crucial Bunny といった当時を象徴する名エンジニアたちがコントロールを担当している。内容は、ダンスホール以前のルーツDJアルバムの典型とも言える仕上がりで、タフでヘヴィなリディムの上で、Hammer がスピリチュアルかつ社会的なリリックを吐き出しながら、DJスタイル特有のトースティングで流れを牽引する。荒削りで土臭い空気感をそのまま刻みつけたようなアルバムで、Channel One黄金期のサウンドをストレートに体感できる。

1977年にサウンド・オペレーターの Berris、セレクターの Wolfman、マイクマンの Jagger、そして Man Fi Bill、Killer らによって結成された、ヨーロッパ初のルーツ・レゲエ・サウンド・システムであり、70年代後半から80年代前半にかけてのUKトップ・サウンドシステムの一つとして君臨していたMoa Anbessa International。1980年にはジャマイカ録音による初のプロダクションをリリースし、サウンド・システムだけにとどまらない本格的なレーベル活動へと歩を進める。その歩みをダブの視点から総括する本作『In Dub』は、荒削りながらも骨太なルーツ・リディムに、当時のUKサウンドシステム特有のエネルギーが刻まれていて、ロンドンで最も熱い時期を駆け抜けたサウンドの生々しい記録となっている。


ロンドンの即興家ロリー・ソルターによるLone Capture Libraryのアルバム『All Natures Most Mundane Materials』が〈A Colourful Storm〉から初リマスター&ヴァイナル・リイシュー。本作は現代DIY環境音楽の隠れた傑作で、英国の田園地帯をさまよいながら録音された即興的な音の記録。洒落た環境音楽ではなく、閉塞感からの解放や自然との対話といった感覚が、不器用で荒削りなサウンドとして残されている。スウィンドンからエイヴベリーまでの徒歩21マイルの旅を背景とした、旅の翌日に自宅で一発録り、即興でカセットに記録されたという素朴な音、フィールド録音、ノイズ、テープの質感などが混じり合う、不器用だけれど美しい音の彷徨。土や身体の素材と向き合うという感覚が全編を通じて感じられる、ユニークで私的な旅の記録。

〈Modern Love〉から初登場となる、CarrierとEquiknoxxの中心人物Gavsborgとの共作による7インチ『The Fan Dance』。Carrierが得意とするダブ・テクノ的な精度と、低音を効かせたステッパーズの骨格を軸にしたトラックに、Gavsborgの独特な声が差し込まれ、陰影のあるヒプノティックなムードを形作っている。A面の「The Fan Dance」は、鋭いハイハットや深いサブベースの上を親密な声が浮遊し、空間を大胆に使った音像が印象的で、必要最低限の要素で緊張感を生む、削ぎ落とされたリズムワークが際立っている。B面のダブ・ヴァージョンではさらにミニマルに削り込まれ、音の骨組みだけが露わになったような、冷たくも研ぎ澄まされた仕上がり。


マンチェスターを拠点に活動するプロデューサー、DJのMichael J. Bloodによる『Bloodlines 1』は、クラブ感覚とジャズ由来の柔軟な耳を掛け合わせた、濃密で引き締まった30分のセッションの記録。A面はひとつながりのフローとして展開し、サルソウルのしなやかなグルーヴからデトロイトの推進力、〈Prescription〉を思わせるディープな質感へとシームレスに移り変わっていく。DJセットの流れをそのまま刻みつけたような臨場感が魅力的。一方のB面はよりハードでトラック寄りで、転がるようなベースと煌めく鍵盤がノーム・タリーを連想させつつ、最終的にはセオ・パリッシュ風のタフで少しずらしたビートに着地する。クラブの現場で鳴らすことを前提にしながらも、緻密な耳で組み上げられた一枚。


Aphex Twinがファッションブランド〈Supreme〉のために作ったプレイリストに選曲。イタリアの名ジャズ・サックス奏者/作曲家であり、ライブラリーミュージック界の巨匠サンドロ・ブルニョリーニによる伝説的作品『Overground』が、Sonor Music Editionsから待望の復刻。オリジナルは1970年、観光プロモーション用ドキュメンタリー『Persuasione』のサウンドトラックとして制作されたもので、アンジェロ・バロンチーニ、シルヴァーノ・キメンティ、ジョルジョ・カルニーニらイタリア屈指のスタジオ・ミュージシャンを迎えて録音された。サイケデリックなプログレロックやファズ・ギター、トリッピーなエフェクトを盛り込んだアンダーグラウンドなサウンドから、洗練されたラウンジ・ジャズ、アヴァンギャルドなオーケストレーションまで多彩。ブルニョリーニがライブラリー界で不動の地位を築いた代表作のひとつ。本作収録の「Roxy」はエイフェックス・ツインがファッションブランド〈Supreme〉のために作ったプレイリストに選曲されている。ブルニョリーニの独特でサイケデリックかつジャズやファンクを融合した音楽は現代の視点で聴いても興味が尽きないものとなっている。音源はオリジナル・マスターテープから丁寧にリマスターされ、ジャケットにはウンベルト・マストロヤンニによるオリジナル・アートワークを忠実に再現。

ニューヨークのアンダーグラウンドMC Sensationalと、ブラジル出身のプロデューサーBruno Tonisiによる、奇妙で幻想的な音のやりとりを記録した作品『Sensational Conversations』が、サンパウロ拠点のオブスキュア系発掘レーベル〈Lugar Alto〉より登場。2人は実際に対面したことはなく、Brunoが憧れの存在だったSensationalにコンタクトを取ったことで、このプロジェクトが始まった。ただしこれは普通のコラボではなく、まるで壊れかけたラジオを通して交信しているような、ノイズまじりの「符号」のような音楽。アルバムはヒップホップを土台にしているが、その形を大胆に解体。GRMがNYのロフトで汚れ仕事を始めたようなサウンドデザインで、ぼやけた声、壊れたビート、不安定なリズムの中に、ふとした瞬間に感情がにじみ出る。その不安定さや歪みにこそリアルな手触りがある一枚!


大推薦!Anyことアナスタシア・パテリスによる新作『MEGA MERCY』が〈sferic〉より登場。クレタ島でのスクワット生活と教会のスピーカーから鳴った深夜のギリシャ正教の説教から着想を得たという、非常に個人的でユニークな作風で、ビートテープやフィールド録音の断片、粗野なサンプルが雑然と組み合わされながらも、どこか禅的な静けさや慈しみが感じられる構成になっている。ハープの音が精神的な軸として通底していて、そこにティルザやアストリッド・ソンネ、ナラ・シネフロあたりに通じる雰囲気が漂う。全体を通して、都市の喧騒から離れたスローで曖昧な時間感覚が支配していて、どの曲も明確な展開を持たず、湿った夜のような、浮遊する感覚が続く。焼けた地中海の風景と内省的な音の断片が織りなす、いびつで美しい幻視の記録。


(数量限定/日本語帯付/解説書封入)深呼吸 ── 心をほどき 太陽を迎える
ブライアン・イーノと並ぶアンビエント巨匠・ララージが、およそ8年前に〈ALL SAINTS RECORDS〉より発売したソロ作品。来日を記念して堂々の新装・日本語帯付盤でリリース決定!
1943年生まれ、ブライアン・イーノと並ぶアンビエントの巨匠にして生ける伝説、ララージ。ジョン・ケイル(ヴェルヴェット・アンダーグラウンド)、ハロルド・バッド、ビル・ラズウェル、ファラオ・サンダース、細野晴臣など、ジャンルも国境も超えたコラボレーションを重ね、オーディオ・アクティブとの『The Way Out Is The Way In』でも日本の音楽シーンに確かな爪痕を残した。そして、2025年9月には、6年ぶりの来日公演を控えており、同月にリリースされるUSインディ・シーンの至宝、ビッグ・シーフの最新アルバムにも参加するなど、精力的な活動と唯一無二性で世界中の音楽家やリスナーに影響を与え続けている。
今回、堂々の新装・日本語帯付盤でリリースされる本作『Bring On The Sun』は、2017年に〈ALL SAINTS RECORDS〉よりリリースされたソロ作品。〈International Anthem〉や〈Leaving Records〉などで多彩な作品を連発し、2024年にもララージとコラボしているLAシーンの立役者、カルロス・ニーニョがプロデュースとミックスを担当し、ダブ・テクノシーンのレジェンド、ポールことステファン・ベトケがマスタリングを担当。緻密かつ繊細な仕事で名高いポールが、ララージのアンビエント作品でもその手腕を遺憾無く発揮している。今回、6年ぶりの来日公演を記念して発売される日本語帯付盤にはCD・LP共に原雅明氏による解説書を封入。


アフリカ大陸各地の伝統音楽とテクノ、ベース・ミュージック、ダブを融合して完成させたトライバル・ベース快心作!
ボイラー・ルームの出演で話題を呼び、〈On The Corner〉よりリリースした前作『Vexillology』はMixmag、The Guardian、Resident Advisor、そしてここ日本では ele-kingでも絶賛を受けたモロッコ出身のDJ/プロデューサー、Guedra Guedraが〈Domino〉傘下の〈Smugglers Way〉よりセカンド・アルバム『MUTANT』をリリース!
Guedra Guedraのサウンドは、ビジョナリーな電子音楽とアフリカ大陸各地の音楽的伝統がまばゆく融合したものである。モロッコ出身のプロデューサー、Abdellah M. Hassakによるこのプロジェクトは、本作『MUTANT』において、アナログ・シンセやドラムマシンから生み出されるリズムと音を基盤に、モロッコ、タンザニア、ギニアなどを旅して採集した打楽器の断片やフィールド・レコーディングを融合させている。
アルバムは、アイデンティティ、パン・アフリカニズム、アフロフューチャリズム、脱植民地主義といったテーマを探求し、大陸の音楽的遺産とテクノ、ベースミュージック、ダブの要素の橋渡しをしている。「自由に作曲できるエネルギッシュなものを作りたかった」とAbdellahは語る。「アフリカやディアスポラの音楽を革新的に探求しつつ、文化的な響きとリズム、ベースのヴァイブスを感じられるようなサウンドを目指した」
このアルバムに収められた楽曲は、アフリカのポリリズムの豊かさを称えると同時に、それが長らく西洋的な論理や標準化のモデルによって形成された技術的ツールや思考の枠組みによって周縁化されてきた現実に挑んでいる。「主流の音楽制作ツールは、非西洋的な文化表現の深みや繊細さを捉えるのが苦手だ」とAbdellahは指摘する。「非線形のリズムや意味のある沈黙、コミュニティ主導のダイナミクスなどが、他文化では不可視化されてしまう。だからこそ、音楽や技術を脱植民地化するとは、そうしたツールの根本を問い直し、他の世界観を受け入れられるような設計に再構築することなんだ」
"Guedra Guedra"という名前は、サハラ地方のモロッコの伝統舞踊を指すと同時に、皮を張ることで太鼓として使える調理鍋の名前にも由来している。カサブランカで生まれ育ち、現在はマラケシュと行き来しながら活動するAbdellahは、若い頃、メタルやレゲエ、ロックなど様々なバンドでベースやドラムを担当していた。やがて、Aisha Kandisha’s Jarring Effects、Muslimgauze、Badawiといった、モロッコの伝統音楽と電子音を融合させたプロデューサーたちの作品に触れ、エレクトロニック・ミュージックやダブに傾倒していった。
2020年のEP『Son of Sun』と2021年のデビュー・アルバム『Vexillology』(On The Corner Recordsよりリリース)では、ダブステップ、フットワーク、ヒップホップのベース重視のリズムに、サンプリングした声や打楽器、楽器、さらには鳥のさえずりや波の音といった環境音を加えていった。
『MUTANT』ではこれらの革新をさらに発展させ、より多様なパン・アフリカンのポリリズムをダンスフロアに持ち込んでいる。Guedra Guedraの音楽は、レジスタンスとしての表現であり、脱植民地化のプロセスでもある。抑圧された声やアフリカの存在を情熱的に受け入れる空間を想像させ、芸術の領域における権力関係への問いかけを促す。「音楽創造と祝祭の場を再取り込み(reappropriation)することは、アフロフューチャリズムにおいて極めて重要なのです」とAbdellahは語る。「それは権力関係を覆し、文化や祖先の知を称揚し、記憶、所有、アクセスといった問題を脱植民地主義の議論の中心に据えている」。
『MUTANT』は、オーガニックとエレクトロニックが巧みに融合した革新的な作品である。Guedra Guedraが使用するサンプルやフィールドレコーディングは、アフリカの多様なフォーク音楽の歴史と遺産を称えると同時に、ドラム・プログラミングやシンセによって、それらを現代のダンスフロア向けに再解釈している。


Chaka KhanやShabaka Huchingsとのコラボレーションでも知られ、Gilles Petersonも惚れ込む現代最高峰ハープ奏者/作曲家のAlina Bzhezhinskaと、イビザを拠点に活動を続け、John DigweedもフックアップするDJ/プロデューサーのTulshiがコラボレーション作品を発売!
本作は雨をテーマとして記憶と感情の変化を描いた作品で、失うことで清められ、再生によって花開き、静かな内省の中で育まれる力強さ−−そうした人生のサイクルが美しく表現されている。
アルバムの核となる楽曲「Journey Home」は、“帰る”ということの意味を問うエモーショナルでメディテーティブな一曲で、変わってしまった場所に戻ることの重み、そして“帰る場所”が実際の地理ではなく、心の状態なのではないかという問いを投げかけている。
アブストラクトにうごめく電子音、ダブテクノ由来のざらついたテクスチャー、主張は控えめながらも心地良いグルーヴを生み出すビート/パーカッション、そして幻想的でディープに響き渡りながらも親しみやすい独特のサウンドを描くハープの演奏が絡み合うことで生まれた珠玉のサウンドスケープ。

オリジナルは1975年に〈Sunshot〉からリリースされた、ホレス・アンディがフィル・プラットのもとで録音した1972〜74年の音源をまとめたアルバム『Get Wise』。シングルで出ていた名曲群を中心に構成されていて、「Money, Money」や「Zion Gate」といった代表曲の別ヴァージョンも収録されている。オーティス・レディングやスモーキー・ロビンソン、そしてアルトン・エリスに影響を受けたアンディ独特のファルセットが素晴らしく、バックを固めるのはソウル・シンジケート・バンドで、スライ&ロビーやファミリー・マン・バレット、チナ・スミスら名手が参加。録音はチャンネル・ワン、ブラック・アーク、ダイナミック・サウンド、ランディーズといった伝説的スタジオで行われ、リー・ペリー、アーリー・トンプソン、アーネスト・フー・キムら超豪華メンバーがエンジニアを務めている。ルーツの真髄に迫るソウルフルな内容で、70年代ジャマイカ音楽を語るうえで外せない作品で、ホレス・アンディの初期の魅力を凝縮した決定版。

オリジナルは1978年に〈High Note〉よりリリースされたThe Revolutionariesの代表作のひとつ『Dub Expression』。録音はデューク・リードの甥であり、後に数々の名作を手がけることになる名エンジニア、エロル・ブラウンが担当。舞台はトレジャー・アイル・スタジオで、マーシャ・グリフィス、ジョン・ホルト、デニス・ブラウンらの楽曲をベースに、ダブ仕様に再構築したものが収められている。屋台骨を支えるのは、スライ・ダンバーの鋭いドラミングで、揺るぎないビートに導かれ、70年代末のジャマイカの緊張感と高揚感がそのまま刻み込まれている。本作が歌い手ではなくバンド名義で出されたのは、プロデューサーのソニア・ポッティンジャーの判断によるもので、個々のシンガーを超えて、チャンネル・ワンのハウス・バンドとして黄金期のサウンドを象徴していたバンドそのものが前面に打ち出されている。その結果、生み出されたものは重量感あふれる、濁りのないダブの真髄。ダブというジャンルの中でも屈指の完成度を誇る一枚となっている。


Bitchin Bajasによる、2022年の『Bajascillators』に続く新作『Inland See』。流動的で瞑想的なサウンドスケープを描き出した本作は、ツアー中に書かれ、シカゴのElectrical Audioでライヴ録音されており、リバーブなどの後処理を一切加えず、部屋そのものの空間感を生々しく封じ込めている。リアルタイムで呼吸を合わせるトリオの一体感がじかに伝わってくるような収録された全4曲は、それぞれ独立した表情を持ちながらも、ゆるやかに繋がり合い、ひとつの大きな流れを形づくる。透明度の高い音の層が浮遊し、ミニマルな繰り返しに穏やかな推進力が宿る様子は、まるで海に身を浮かべる感覚や、風船がゆっくり上昇していく感覚にも近い。アンビエントやミニマル・ミュージックの要素を取り入れつつも、演奏の身体性が強く残った有機的で生きた響きになっており、シンプルでありながら精緻、緊張感と安らぎを同時に孕み、どこか新しい扉がひそやかに開いていくような瞬間に出会える一枚。

Natural Information SocietyとBitchin Bajasという、ドローンへの深い理解と霊的な探究心を持つグループ同士による2015年の共作『Automaginary』が2025年リプレス!音楽的には、アフロ・グルーヴ、クラウトロック、自由な即興的なジャズ、サイケデリック、アンビエント、4つ打ちのビート、ミニマリズムなど、ありとあらゆる要素が曖昧に融合したサウンドで、グナワ音楽に使われる3弦のリュート「ギンブリ」のミニマルなパターンと、Bitchin Bajasが得意とするアナログ・シンセやヴィンテージ機材によるサイケなレイヤーが混ざり合っている。ミニマル・ミュージックの没入性とジャズ由来の自由さが共存しており、Natural Information SocietyとBitchin Bajasという、2つの部族が出会い、未来の儀式をやってみせたような、ひたすら時間が溶けていくような一枚。

未体験の方はこの機会にぜひ!シーンの枠組みを越えて多大なリスペクトを浴びる、我らが音の錬金術師、ジム・オルークが2001年に〈Drag City〉から発表したアルバム『Insignificance』が2025年リプレス。Jeff Tweedyに、Darin Gray、Ken Vandermark、Rob Mazurek、Tim Barnesら豪華面々を引き連れて作り上げたチェンバー/アート・ロックの名作!


〈Drag City〉配給。Joshua Abrams参加!Jim O’Rourkeの名作群でのドラミングを筆頭に、Tony Conrad、Faust、Sonic Youth、Wilco、Silver Jews、John Zorn、Stereolab…と数え切れないほどの先鋭的アーティストたちと共演してきた名手Tim Barnes。2021年に若年性アルツハイマーと診断された彼が、その後に取り組んだ『Lost Words』に続く、Tim Barnesの未発表ソロ音源集第2弾。『Noumena』が自身のレーベル〈QUAKEBASKET〉より登場!本作は楽器の演奏というよりも、音そのものの在り方を探るような試みで、フィールドレコーディング、環境音、オブジェクトの擦過音、微細なパーカッション。それらが時間の中で溶け合いながら、ゆっくりと立ち上がってくる。沈黙や余白、聴覚の境界線をじっと見つめるような、深く静かな世界に焦点を当てた作品。ジャズ、ポストロック、即興、アヴァンギャルド……様々な音が行き交いながら、音に向き合い続ける彼の、静かで強靭な意志が感じられる一枚。『Lost Words』と対を成す、深く静かなリスニング体験。