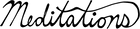NEW ARRIVALS
1362 products


Oren Ambarchi、Johan Berthling、Andreas Werliinによるトリオ作『Ghosted III』が〈Drag City〉より登場!ジャズやクラウトロックの感覚を土台にしつつ、今回はより自由でゆるやかな空気をまとった一作で、前2作に比べて、アメリカーナやドリームポップ、ブルースといった新たな要素もにじみ出ていて、細部のニュアンスにフォーカスしたサウンドが特徴的。冒頭曲では、チリチリとしたギター、よれたリズム、ほどけたベースが絡み合い、フィリップ・グラス風の浮遊感が心地よい。曲ごとにテンションを緩めたり高めたりしながら、美しいドリームポップ風ポストロックへと昇華。全体として、即興的な緊張感は保ちつつも、より開放的で感覚的な作風で、シリーズ中でも特にメロディアスで親しみやすい内容になっている。


Sir Richard Bishop(Sun City Girls)によるひとりアコースティック・ギターだけで挑む、原始衝動むき出しの一枚はアメリカン・プリミティヴを踏まえつつも、そこにインド古典音楽のラーガの解釈を織り込み、秩序や安定から外れたリズムと動きに焦点を当てた、荒々しい独奏集。彼が語るところによれば、目指したのは基本への回帰で、エフェクトも電気もオーバーダブも一切なし、あるのはギター一本と自分の手だけ。アメリカン・プリミティヴが「原始」と名乗りながら、実際には整然としすぎていることへの反発から、あえて無鉄砲に、予測不能な展開を打ち出す。その姿勢は、山奥で誰からも教わらず独自のフォークロアを鳴らす孤高のヒルビリーをイメージしたものだという。『Salvador Kali』『Improvika』『The Freak of Araby』といった探求的な作品群で培ってきた感覚を、ここでは極限まで削ぎ落としており、9曲それぞれが、深い森をひとり分け入るかのような探索であり、外界と切り離された音楽の放浪記でもある。ヒルビリーの神秘家による異形のフォーク伝承。


ブラジル・サンパウロ郊外ディアデマから登場したDJ Kによる、ファヴェーラのリアルを突きつける最新作『Rádio Libertadora』が〈Nyege Nyege Tapes〉より登場。17歳からFL Studioで制作を始め、わずか数年でブラジリアン・ファンキの枠組みを塗り替えたDJ K。独自に生み出したBruxaria(魔術)と呼ばれるスタイルは、暗く、ノイジーで、サイケデリック。前作『Pânico no Submundo』でその片鱗を見せたが、本作ではさらに過激で、政治的な鋭さを増している。アルバム冒頭、1969年の軍事独裁時代に共産ゲリラ指導者カルロス・マリゲーラが地下ラジオで放送した反体制スピーチをサンプリングし、「軍事独裁に死を!」と高らかに宣言。MC Renatinho Falcãoを迎えたそのトラックでは、金属質なノイズ、爆音ベース、歪んだディストーションが入り乱れ、ファヴェーラを「見えない戦争」の戦場として描き出す。90年代ブラジルのプロテスト・ラップに通じる闘争のスピリットと、腐食した電子音の荒野。『Rádio Libertadora』は単なるアルバムではなく、サンパウロの地下から鳴らされるマニフェストとも言うべき一枚。

中東地域のネットカルチャーとグローバル・ベース/クラブ・ミュージックの接点を捉え続けてきた〈HEAT CRIMES〉から、注目のコンピレーション『REEL TALK - BEST OF DOUYIN TRACKS』が登場。中国のショート動画プラットフォーム「抖音(Douyin)」上で流通したサンプリング音源やクラブトラックをキュレートし、カットアップ、スクリュー、トランス、スピードコア、トラップ、アンビエントまでを雑多に飲み込む全20曲。ネット特有の速度感と無作為さ、そして奇妙なエモーションが交錯する、デジタル以降のサウンド・アーカイブとしての一枚。カルト的人気を誇るシリーズ最新章。

2021年東京、ハリクヤマクの曲だけでDJをするという珍しい機会があった。普段だとエフェクターやミキサーなど、まぁまぁの量の機材を運んでライブ・ダブミックスをしているんだが、DJセットときた。
しかし、リリースの有無に関わらず、自分の中で一度完成した曲だけをプレイするのはDJをやってて、自分が面白くないなと思った。そこで、フライトまでの2日間、色々な曲のダブミックスを録音し、それをCD-Rに焼いて持っていったのである。沖縄に帰ってしばらくして、そのCD-Rを聴き返したら、色々と荒いなと感じながらも、それ含め良い!と思い、配信することにした。それが『島DUBPLATE for Tokyo 2021』である。
それからまた月日は経ち、2024年。なんとこれをレコードにしてくれるという話がきた。最高だ!最高だけど、レコードにするには、惜しい曲や物足りなさがある。配信とレコードとでは訳が違う。一発録りの2ミックスだから、重ねるしか無いと思った。CD-Rから曲を選び、
A2 "Ayahaberu"には盟友MAKI TAFARIによるフルートソロをオーバーダブ。
A4 "Turubaimun"にはAKANMIMANにトースティングしてもらった。彼にとっては初めての録音だった。
B1" Kuduchi Behshiはスプリングリバーブを叩いたノイズやシンセをオーバーダブ。
また、レコード化のために新しくダブミックスも録音した。
A3 "Pacific Dub"は個人的には沖縄レゲエ史上最高の曲、石垣吉道の"Key Stone"をリディムを作りかえダブミックス。
B4 "Dub Season"はこちらも盟友、稲嶺幸乃との共作である”四季口説"をダブミックスしている。
Text by HARIKUYAMAKU


レバノン出身のバンドSANAMによる2ndアルバム『Sametou Sawtan』。タイトルはアラビア語で「私は声を聞いた」という意味で、霊的でも不気味でもあるこの言葉が象徴するように、その音楽は音と言葉が心を揺さぶり、聴く者を今この瞬間へと引き戻す。ロックやジャズの自由な枠組みとアラブ音楽の深い伝統がぶつかり合い、情熱的なバラードと荒々しい即興演奏が交錯。詞作は前作同様、古今東西の詩や歌から引用し、現代的な意味を与え直すもの。エジプト民謡を再構築した「Hamam」、レバノンの現代詩人ポール・シャウルの詩をハードロックで爆発させる「Hadikat Al Ams」、12世紀の詩人オマル・ハイヤームの詩を用いた「Sayl Damei」やタイトル曲などが収録されている。過去の遺産を借りながら、燃えるようなライブ感と深い感情表現で、現代アラブ圏の新しいサウンドを切り拓く一枚!

水玉消防団の1985年作、セカンド・アルバム『A Skyfull of Red Petals』が〈SPITTLE MADE IN JAPAN〉から再発。本作も、前作に引き続き鋭く挑発的で、強烈で、唯一無二で、何ものにも媚びない。このバンドが「自然現象のような存在」であることを強く印象付ける一枚。実験音楽の巨匠フレッド・フリスが惚れ込み、ミックスを手がけている。ヴォーカルの神楽と天鼓、まったく異なる声とスタイルがせめぎ合いながらも調和していく様は、まるで即興演劇のような迫力で、演奏も歌も「うまさ」ではなく「勢い」と「意志」で押し切っている。そのぶん演奏の空気感や緊張感が濃く、混沌の中に一種のユーモアや祝祭性があって、それがミズタマ消防団の真骨頂でもある。ジャンルでいえば、ポストパンク/アヴァンギャルド/ノーウェイヴあたりを軸としつつ、単なるカテゴライズではすくいきれない、“表現としての音楽”がここにある。日本のアンダーグラウンドが世界のアヴァンシーンとリンクしていた稀有な瞬間の記録。

オリジナルは1981年にリリースされた、女性だけのバンドで、妥協のない異端の存在として知られ、当時の日本のアンダーグラウンド・シーンの中でも突出した個性を放っていた水玉消防団の伝説的デビュー作『A Maiden's Prayer DA-DA-DA! 』が〈SPITTLE MADE IN JAPAN〉より再発。アヴァンギャルドなポストパンク、演劇的要素、実験性が渾然一体となった、“もうひとつの日本”を体現する鮮烈なアルバムで、フレッド・フリスもライヴを観て神楽と天鼓という対照的な二人のボーカルの絡みが特に印象的だったと語っている。カオティックで尖った音楽性を持ちながら、メンバー同士の呼吸や空気感に独特の親密さがあり、単なるノイズや過激表現を超えた、共同体としての美学と緊張感が共存するサウンド。パフォーマンス的な要素も強く、音楽というより“事件”に近いインパクトを持っていたバンドの当時の熱量を閉じ込めた貴重な記録


日本、京都拠点に活動するG VERSION IIIによる、サウンドシステムカルチャーに対する深い敬愛から生まれた実験的ステッパー・デジタルダブがRiddim Chango Recordsの9番として登場!昨年Digital Stingレーベルからリリースされたカセットテープ・アルバムが話題を呼んだ関西が誇る才能、G VERSION III。80's、90's UKダブの影響とコズミックなシンセサウンドが絡み合う重厚かつスローな4つ打ちステッパーなトラック1、明らかにフロアバンガーな強烈ステッパーズのB1,B2とサウンドシステムにアジャストするヘヴィーウェイトな作品。
デジタルマスタリングはe-mura (Bim One Production)、ラッカー・カッティングエンジニアには近年メキメキと頭角を表ているSaidera MasteringのRei Taguchiが担当。サウンドシステムの鳴りは安定保証!


Katatonic Silentioによる、2023年に自然派フェス La Nature のKatatonic Silentioによるライヴをそのまま収めた濃密な記録が、フランスの新興レーベル〈Fleur Sauvage〉の第一弾リリースとして登場。抽象的なエレクトロニクス、ザラついたノイズ、映画的なアンビエンスが交錯する、ジャンルを横断する内容で、不安定なテンションが全体を貫いている。時に静寂の瞬間を挟みつつも、突如として鋭角的で荒々しい爆発へと跳ね上がる、そのダイナミクスの幅がある種、儀式的。低域のうねりが身体的な感覚を呼び起こし、表層では粒立ったテクスチャーが絶えず変化する様は、曲としての整合性よりも場と身体が一体化した経験を重視しており、スタジオ作品というよりも生きられた音響の記録と感じられる。唐突に立ち上がって、気配のように漂い、また不意に消える音を聴いているうちに、ただその音の中に居るしかなくなるような没入感あふれる一枚。

スペインはマドリードのレフトフィールド・テクノレーベル〈Alpenglühen〉より、Vandと!nertiaによる新ユニットVanertia のデビュー作『Kronicles』が登場。クラシックなダブ・テクノの文脈が音の核にあると言える作風で、深く沈み込むようなコード音やエコーの広がりが全体を包み込みながら、細やかに刻まれるパーカッションが緊張感を与えている。リズム面では、淡々とした4つ打ちの推進力と、ずらしたビートの絡みが交差し、硬質さと柔らかさを同時に感じさせるバランスを構築しており、低域は重すぎず、あくまで有機的に脈打ちながら全体を支えている。クラブでも機能する推進力を持ちつつ、ヘッドフォンで浸っても奥行きを味わえる没入的な仕上がりは、ダブ・テクノの伝統に根ざしながら、現代的な質感と繊細な構築力を備えた充実作!


韓国のチェリストであり作曲家、Okkyung Leeによるアルバム『Just Like Any Other Day (어느날): Background Music For Your Mundane Activities 』が〈 Shelter Press 〉より登場。タイトルに「あなたの日常のためのBGM」と添えられている通り、この作品はこれまでとは異なる作風で、アンビエント、ミニマリズム、バロック的要素が交錯する、親密で繊細な音の世界を描いている。これまで自由即興の最前線で活動してきた彼女だが、近年はより作曲的なアプローチへとシフト。本作もその流れにあり、アメリカ生活を終え韓国に戻ったことで再び見つめ直した文化や記憶、人生の変化が反映されている。4年間、孤独な環境で少しずつ作り上げた全9曲は、従来の「実験音楽」的な形式美や技巧を捨て、聴く人の日常にそっと寄り添うような音楽となっている。今回は、彼女の象徴だったチェロも一切使用せず、キーボードやコンピュータ、安価なカセットレコーダーで制作。無理に聴き込むのではなく、気づけばその中に包まれているような音の空間。控えめな旋律や反復が、記憶や孤独と静かに共鳴し、日常の背景に溶け込んでいくような音楽。

MAJESTIC ARROWSの唯一作、シカゴのスウィート・ソウルの隠れた名盤『The Magic of The Majestic Arrows』が〈Numero Group〉よりめでたくも50年ぶりに再発!オリジナルは70年代にArrow Brown自身のレーベル〈Bandit〉から発表したもので、制作はシカゴ・ブロンズヴィルの彼の拠点にて。そこは自宅であり、ハーレムであり、地下スタジオでもあったという、まさにDIY精神が詰まった空間だった。50年代ドゥーワップのストリート感と70年代ソウルの豊かなストリングスが交差するような仕上がりになっている。歌っているのは彼の10代の娘Tridiaと、The Moroccosのファルセット使いLarry Brown。バックはChosen FewとScott Brothers、アレンジはBenjamin Wright、ジャケットはThe WindのEugene Phillipsが担当。個人的でいてどこか魔法めいた響きを持つ、まさにソウル史の知られざる宝石のような一枚。


1980年代初頭のパンクバンドThe Freezeから発展した、スコットランド出身のアーティスト、CinderによるソロプロジェクトCindytalkの3rdアルバム『The Wind Is Strong - A Sparrow Dances, Piercing Holes in Our Sky』は、イギリス人監督イヴァン・アンウィンの実験映画のサウンドトラックとして制作されており、フィールドレコーディング、物悲しいピアノの小品、そして不穏な金属音が交錯する、Cinder自身が「ambi-dustrial」と表現した独特のサウンドパレットが特徴的。長らく入手困難だった本作は、Cindytalkのディスコグラフィーの中でも、最も捉えどころがなく、冒険的な作品の一つで、ミュジーク・コンクレート、心に響く夢想、荒涼とした美しさが融合しており、映像がなくても、夕暮れの森や薄暗い廊下といった、映画的な情景を思い起こる。Cinder自身は「Cindytalkの脱線」と注記していたものの、歌を中心としたポストパンクから大胆に逸脱し、未知の領域へと足を踏み入れた、キャリアを俯瞰する上で重要な作品。


1980年代初頭のパンクバンドThe Freezeから発展した、スコットランド出身のアーティスト、CinderによるソロプロジェクトCindytalkによる90年代インダストリアル、エクスペリメンタル・ロックの隠れた名盤。1994年にリリースされた当時から「スコットランド独立への呼びかけ」として構想され、過去から現在に続く独立への衝動を音で掬い上げながら、ポストパンク、インダストリアルの文脈の中で唯一無二の存在感を放ってきた作品。アルバムは、イギリスのフォークソング「The First Time Ever (I Saw Your Face)」をボーカルソロで痛々しく歌い上げる形で始まり、その後、Cindytalkの代表曲「A Song Of Changes」へと続く。そこからは、熱狂的な悲歌、思索的なスピリチュアル、ノワール的な抽象性、グラスゴー出身の作家Alasdair Grayが参加したスポークンワーズ、バグパイプのドローン、終末的なポストパンクなど、様々なスタイルが不規則に展開。This Mortal Coilとの接点から、90年代のハードコア・テクノ、さらにはMegoでの電子作品群へと繋がるCindytalkの活動史の中でも、不安定で困難な環境のもと制作された『Wappinschaw』は、最も闘争心と祈りが濃縮された瞬間を刻んでいる。


アフロ・コロンビア音楽新世代を世界に知らしめたシステマ・ソラールの中核メンバーによるプロジェクト、エル・レオパルドの2ndがリリース!カリブ海のパーカッション、アナログ・シンセ、ディープ・ベース、エレクトリック・ギター、そして彼のトレードマークとも言えるコロンビアの伝統的フルートであるクイシ、トランペットの催眠術のようなバイブレーションによって無限の宇宙を永遠に漂っているような気分にさせてくれるとんでもない内容!1970年代から80年代にかけてのカリブ海のトロピカル・サイケデリアへのオマージュとテリー・ライリーやクラフトワーク、マッド・プロフェッサーからの影響が結びつく独自のサウンド!


約2年振りとなるKendra Morris待望の最新作『Next』。Colemine Records の Leroi Conroy との共同プロデュースのもと、オハイオ州ラブランドのスタジオでヴィンテージ機材を駆使して録音。Tascam 388 を通した音像は、ツヤや洗練よりもざらつきや手触りを優先し、温かみのあるアナログ質感を全編にまとわせている。ゲストには Delvon Lamarr Organ Trio の Jimmy James、The Black Keys 周辺で知られる Ray Jacildo が参加。作品全体はどこかローファイなコンセプト・アルバムのような趣きがあり、ジャケットにある古いボードゲームやレトロなテレビ番組に通じるDIY感覚を下敷きにしているよう。音楽的には、ドゥーワップやブームバップ、ロックステディといった異なる要素を縫い合わせるように展開し、まるでニューヨークの古き良き記憶をコラージュしたような世界を描き出す。洗練よりも遊び心や想像力を優先するように、完璧さとは無縁で、むしろその不完全さの中にこそ息づくハートとイマジネーションが詰まったアルバム。カラフルでいてどこか懐かしいサウンドに、心に響くソウルフルな歌声が溶け合う一枚。

オリジナルは1973年に〈Bacillus〉からリリースされたセカンド・アルバム。前作のヴォーカル主体のプログレ・ロック路線から大きく舵を切り、ジャズ、エスニック、アシッド・ロックを自在に混ぜ合わせたサウンドへと進化した作品で、メンバーも刷新され、マルチインストゥルメンタリストの Eddy Marron、ベースの名手で創設メンバーの Reinhard Karwatky、そして超絶技巧のドラマー Peter Giger のトリオ編成になっている。盤全体に漂うスペーシーな即興感覚、エスニックな音色の実験、そして強烈なジャズ・フィーリングが渦巻いており、ロックでもジャズでもないはざまの領域に立ち、独自の美学を築いた作品。ドイツ産ロック史の中でも屈指の異色盤として知られる、技巧派トリオが織りなす異世界ジャズ・ロックの名品。

オリジナルはAlvin “GG” Ranglin のレーベルから1981年にリリースされた、グレゴリー・アイザックスの代表的コンピレーション第2弾。全10トラックで、彼特有のスムースでメローなルーツ・レゲエを存分に味わえる内容になっている。「Border」や「Village Of The Under Priviledge」、「Tumbling Tears」など、都会の影や弱者の視点を繊細に描く歌詞と、Isaacs の甘くしっとりとしたヴォーカルが印象的で、バックのリディムはあくまで落ち着きのあるルーツ寄りで、夜の静かな時間にぴったりの温度感。甘くしなやかな声で都会の影を歌う、ルーツ・レゲエの名手グレゴリー・アイザックスの極上メロウ集!

80年代初頭、ジャマイカのルーツ、ダンスホール・シーンで頭角を現した Delton Screechie による82年作極上ルーツ・アルバムの公式再発盤。録音は Harry J’s スタジオでミリタント・リズムをバックに行われ、その後キング・タビーのスタジオでヴォーカルとミックスが施されている。タイトル通り、アルバム全体を通して社会的メッセージや都市の苦境を歌うルーツ歌詞が中心で、Screechie の表現力豊かな声が、硬質で骨太なリディムと絡み合う。タフなリズムに支えられたそのいなたい歌声は、初期80年代ジャマイカン・ルーツの熱気を封じ込めた名盤。

ジャマイカン・ルーツ、ダブの深淵を掘り下げるリイシュー、Tafari All Stars の『Rarities from the Vault Vol.2』は、〈Wackies〉、〈Aires〉、〈Earth〉などの初期レーベルからのレアトラックやダブプレートを集めた掘り出し物集。注目は、Leroy Sibbles と Stranger Cole をフィーチャーしたダブプレート群。Sibbles は Studio One 時代の自身の「Guiding Star」リズムを Bullwackies でリワークして提供しており、ファンにはたまらない逸品。また、冒頭のトラックでは、Little Roy と共に Glen Brown の「Wedden Skank」を大胆に乗っ取る演奏も収録。全体を通して、粗削りで土臭いダブのエッセンスがぎっしり詰まったアルバムで、単なる過去音源の寄せ集めではなく、当時のサウンドシステム文化やレコーディング現場の空気感まで感じさせる、まさに掘る楽しみのための一枚。

オリジナルは1979年リリースの、ジャマイカのルーツDJシーンを代表する一人、Prince Hammer による重要作。バックを固めるのは Channel One の最強リズム隊 The Revolutionaries。さらに Prince Jammy、Errol Thompson、Crucial Bunny といった当時を象徴する名エンジニアたちがコントロールを担当している。内容は、ダンスホール以前のルーツDJアルバムの典型とも言える仕上がりで、タフでヘヴィなリディムの上で、Hammer がスピリチュアルかつ社会的なリリックを吐き出しながら、DJスタイル特有のトースティングで流れを牽引する。荒削りで土臭い空気感をそのまま刻みつけたようなアルバムで、Channel One黄金期のサウンドをストレートに体感できる。

1977年にサウンド・オペレーターの Berris、セレクターの Wolfman、マイクマンの Jagger、そして Man Fi Bill、Killer らによって結成された、ヨーロッパ初のルーツ・レゲエ・サウンド・システムであり、70年代後半から80年代前半にかけてのUKトップ・サウンドシステムの一つとして君臨していたMoa Anbessa International。1980年にはジャマイカ録音による初のプロダクションをリリースし、サウンド・システムだけにとどまらない本格的なレーベル活動へと歩を進める。その歩みをダブの視点から総括する本作『In Dub』は、荒削りながらも骨太なルーツ・リディムに、当時のUKサウンドシステム特有のエネルギーが刻まれていて、ロンドンで最も熱い時期を駆け抜けたサウンドの生々しい記録となっている。


ロンドンの即興家ロリー・ソルターによるLone Capture Libraryのアルバム『All Natures Most Mundane Materials』が〈A Colourful Storm〉から初リマスター&ヴァイナル・リイシュー。本作は現代DIY環境音楽の隠れた傑作で、英国の田園地帯をさまよいながら録音された即興的な音の記録。洒落た環境音楽ではなく、閉塞感からの解放や自然との対話といった感覚が、不器用で荒削りなサウンドとして残されている。スウィンドンからエイヴベリーまでの徒歩21マイルの旅を背景とした、旅の翌日に自宅で一発録り、即興でカセットに記録されたという素朴な音、フィールド録音、ノイズ、テープの質感などが混じり合う、不器用だけれど美しい音の彷徨。土や身体の素材と向き合うという感覚が全編を通じて感じられる、ユニークで私的な旅の記録。