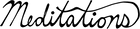NEW ARRIVALS
1053 products


タイ東北部イサーンの伝統音楽モーラムを軸に、ファンク、ロック、ポストパンク、アジアからインド洋圏のリズムを大胆に取り込んだ、バンドの進化形を示すサード・アルバム『Araya Lam』。イサーンの伝統楽器、ポーンラン(木琴)、ピ(笛)、ソー(弦楽器) などを積極的に導入、伝統旋律の魅力を保ちながら、現代的なアンサンブルへと再構築している。生演奏ブレイクビーツ的なグルーヴや、ドラッギーなファンク感も随所に登場し、伝統音楽の素朴さと、クラブミュージック的な反復グルーヴが共存している。モーラムの土の匂いと、都会的なビートが同時に漂う、サイケデリックでトランシー、だけど温かいアルバム。モーラムの根源性と現代的なグルーヴ、サイケデリックな実験精神が結晶した、The Paradise Bangkok Molam International Band の到達点とも言える作品。


ロンドンのサックス奏者、プロデューサー Ben Vince が、サックス、電子音、生楽器を溶け合わせながら独自の都市的儀式音楽を描き出したアルバム『Street Druid』。サックスは旋律ではなく音の素材として扱われ、ロングトーンやブレス、加工された倍音が霧のように漂う。その周囲を、シンセの持続音、声の断片、ギターの残響、ミニマルなドラムマシンが有機的に絡み、さらに Moses Boyd の生ドラムが加わることで、抽象的な音像と身体性が同時に立ち上がる。エレクトロニック、アンビエント、UKジャズ、実験音楽が混ざり合うように、音のレイヤーが重なり合うことで、都市の夜をさまよう、寓話的なストリートのドルイドというイメージが音楽そのものから滲み出るかのよう。Ben Vince の探求が最も豊かに結晶した、都市の夜の濃密な儀式的サイケデリア!

オーストラリア・メルボルンのシンガー・ソングライター Ruth Parker による、ギター、ウクレレ、アコーディオン、ブズーキ、チェロ、マンドリンなど多彩なアコースティック楽器を取り入れたアレンジに、彼女の繊細で親密な歌声が重なるアルバム『Otherwise Occupied』。静かな余白を大切にしたサウンドは、インディ・フォークやシンガー・ソングライターの系譜に位置づけられる一方で、豊かな質感とメロウな響きによってドリーム・フォーク的な側面も感じさせ、聴き手に内省や感情の微細な動きを追体験させるように響く。派手さよりも細部のニュアンスに耳を傾けることで、しみじみとした深みとやさしい気持ちに包まれる一枚。

Bob Jamesが〈CTI Records〉で残した最後の作品にして、彼の洗練されたフュージョン美学が最も完成された形で表れた名盤。Van Gelder Studioで録音されたクリアでリッチなサウンドは、ストリングス、ホーン、エレピが滑らかに溶け合う、CTIらしさを最も端正な形で体現しており、代表曲「Tappan Zee」をはじめ、都会的で爽やかなグルーヴと、耳に残るテーマが印象的。後のスムースジャズの原型ともいえる軽やかな質感がありながら、演奏は緻密で、アンサンブルの美しさが際立つ。George Marge、Gary King ら名手が参加し、アレンジの細部まで丁寧に作り込まれた一枚。


イタリアン・ライブラリー界の巨匠、Alessandro AlessandroniとGiuliano Sorginiによる、民族志向ライブラリー三部作の最終章として1971年に発表された『Alle Sorgenti Delle Civiltà Vol. 3』が、〈Musica Per Immagini〉から再発。アフリカ/オーストラリア/ニュージーランドを題材に、架空の民族儀式を描くようなトライバルなパーカッション、素朴な木管、乾いた質感のサウンドが連なり、70年代イタリアン・ライブラリー特有のサイケデリックな空気が漂う。短い楽曲が連続しながら、ミニマルな反復とドキュメンタリー音楽的な質感が交錯する、架空の民族誌映画を観るかのような作品。

フィラデルフィアのギタリスト、シンガー、Carl Sherlock Holmesが1974年に自主レーベル〈C.R.S.〉から発表した唯一のアルバム『Investigation No.1』。フィリー・ソウルの洗練と、ワイルドなファンクの熱量が同居した、まさに発掘系ソウルの理想形といえる一枚。ワウ・ギターとハモンドが絡む冒頭曲「Investigation」、「Black Bag」「It Ain’t Right」では強烈なドラムブレイクが炸裂。一方で「Your Game」などのメロウ・ソウルでは、フィリーらしい柔らかさと深みが際立つ。捨て曲なしと評される完成度のレアグルーヴ界で語り継がれる名盤。

1971年2月、ノルウェーの現代芸術センターHenie Onstad Art Centreで行われた未発表ライブ音源を収めた、重要なドキュメント。『Fourth』期のメンバーによる演奏で、ジャズ・ロックからアヴァンギャルドへと深化していく転換点のSoft Machineを鮮明に捉えている。エレクトロニクスを通したオルガンやベースが生むサイケデリックな音像、Robert Wyattの有機的なドラミング、そして作曲と即興が溶け合う長尺の展開は、当時のバンドの実験精神をそのまま封じ込めたもの。スタジオ作とは異なる、荒々しくも知的なエネルギーが渦巻くライブ盤。

1950年代から活動するジャマイカの名門バンドで、スカを世界に広めた立役者のひとつとして知られるByron Lee & The Dragonaires。彼らの1960年代前半にリリースされた代表作で、スカ黄金期の明るさ・軽快さ・ダンス性をそのままパッケージした名盤『Plays Jamaica Ska』。軽快でダンサブルなスカ・ビートがひたすら楽しく、身体が自然に動く。メロディはわかりやすく、ポップでキャッチー、ホーンのハーモニーも美しく、アンサンブルはタイト。当時のジャマイカで流行していたスカを、より洗練されたアレンジと演奏力でまとめ上げ、海外に向けてジャマイカの音楽を紹介する役割も果たしたとされる重要作。60年代ジャマイカの祝祭感が詰まった一枚。

ベルギーのジャズ・ピアニストMarc Moulin率いるPlaceboによる1971年発表のデビュー作で、ジャズ・ファンクの深淵とヨーロピアン・クールネスが交差するレアグルーヴの名盤『Ball Of Eyes』。Marc Moulinによるエレピとシンセの浮遊感あるプレイを中心として、ブラック・ミュージック由来のグルーヴとヨーロピアン・ジャズの洗練が融合。J DillaやMadlibなどのヒップホップ・プロデューサーがサンプリングしたことで再評価された本作は、ベルギー産ジャズの最高峰として、今なお新鮮な輝きを放っている。


UKのベース・プロデューサーNo Iconsによる、クラブ・ミュージックの黄金期の記憶を現代的に再構築した最新作『Nothing But Fixes』が〈Modern Love〉から登場。A面の「Nothing But Fixes」は、ざらついたテクスチャと細かく刻まれるビートが交錯し、深夜のフロアをゆっくりと沸騰させるような長尺トラック。B面には、リスボンのダンスフロアを思わせるルーズなスウィングを持つ「Carinho」、鋭いスネアが身体を揺らすハーフステップ「Dojo」、鋭いミニマル・グライム「Echochrome」を収録。ミニマルでありながら空間を切り裂くようなベース・トラック集。

1994年2月22日にローマの Palaghiaccio で行われたライブを収録したアルバムで、カート・コバーンが亡くなるわずか数週間前のツアーということもあり、バンドの緊張感と荒々しさ、そしてどこか不安定な空気がそのまま刻み込まれている。音源はFM放送由来の高音質ソースを元にしていると言われ、非常に聴きやすい仕上がり。「Smells Like Teen Spirit」「Come As You Are」「Heart-Shaped Box」などの代表曲に加え、「The Man Who Sold The World」など後期ツアーならではの選曲も含まれ、当時のバンドの姿をほぼ完全な形で捉えている。現場の空気が強く残っており、ニルヴァーナ最晩年のリアルな姿を感じられる貴重な記録。


Yungwesbsterの『II』などの作品にも参加の、シアトル拠点のプロデューサーMatryoshkaによるデビュー・アルバム『Blasé Saint』。アンビエント、ダブテクノ、ダウンテンポを横断する濃霧のような深い音像は、低く沈むビート、霞がかったシンセ、遠くで揺れる環境音が重なり、まるで夜の都市を漂うような質感。繊細な音響処理と深い空間性、Burial、Shinichi Atobe、Space Afrika、Malibuらの系譜に連なる情緒的なレイヤーを併せ持ったエーテルのようなアンビエンスが、夜の静けさを照らす。マスタリングはRashad Beckerが担当。

エチオピア生まれ、ベトナムとスウェーデンで育ち、ジャズと作曲を背景に持つ実験声楽家 Sofia Jernbergによるソロ作『Voice』。声を単なる歌唱ではなく音の物質として扱っており、収録曲も「Multiphonic I」「Gurgle」「Mouth Synthesizer」「Throat」など、声帯・息・口腔の動きをそのままタイトルにしたような構成で、旋律や言語よりも 声の物理現象そのものが前面に出ている。金属的な倍音、破裂音、動物的なうなり、空気の摩擦音など、声の境界を押し広げる表現が連続し、聴き手は身体の内部を聴くような感覚に包まれる。Meredith MonkやMaja Ratkjeの系譜に連なりつつ、よりノイズ寄りで原初的なエネルギーを帯びた、声の前衛の最前線を示す一枚。

Marc Almondの長年のコラボレーターとして知られ、Nick Cave、Lydia Lunch、Deux Filles、KraftwerkのWolfgang Flürら数々のレジェンドと共演してきたAnnie Hoganによる、ゴシック/ミニマル・シンセ/インダストリアルの境界を漂う、退廃と儀式性に満ちた室内楽『Tongues in My Head』。夢想と悪夢の狭間を揺らめくようなHoganのピアノとキーボードが印象的で、録音・演奏・ミックス・プロデュースをすべてHogan自身が手がけ、エンジニアと同じ部屋に入りライブ録音のように制作されたという背景も、音の生々しさと霊的な緊張感を際立たせている。ピアノの残響、低く唸るシンセ、沈黙の間合いが織りなすサウンドは、Leonard CohenやRowland S. Howardを想起させる退廃的な美しさを帯び、静かに深く沈み込む。Annie Hoganのキャリアを更新するダーク・エレガンスの結晶。


アテネ拠点のパーカッショニスト、サウンドアーティスト Yorgos Stavridisによる、〈Heat Crimes〉からのデビュー作『Solo Percussion』。従来の打楽器アルバムという枠を大きく逸脱し、膜・金属・拾得物・枝・猫のおもちゃ・ポッピングキャンディまで、あらゆる物体を音源として扱うラディカルな作品。 全編がワンテイクの即興演奏で構成され、マイクやスピーカーまでも楽器として扱うことで、フィードバックや空間の反応そのものが演奏に組み込まれていく。金属のきしみ、膜の震え、低周波の圧力、物体同士の摩擦。音の発生源が可視化されるような触覚的サウンドが、録音空間を立体的に揺らす。ミニマルでありながら予測不能な展開は、エレクトロアコースティック、ミュージック・コンクレート、モダン・クラシカルの文脈とも響き合い、打楽器と物体のアニミズムとも言うべき独自の世界を作り上げている。


Magazzini Criminaliが1983年に〈Riviera Records〉から発表した、民族音楽や古典音楽、他人のレコード、環境音、映画音声といった異なる音源を切り貼りし、ムーグやサックスの即興演奏、Marion D’Amburgoの詩的で時に激しい声を重ねたコラージュによる作品『Notti Senza Fine』。フィレンツェのポストモダン演劇集団らしい、Musique Concrèteと実験的ロックの要素が混ざり合う独自の音響世界を形成している。劇場的な緊張感と音の断片が連続する構成は、彼らのパフォーマンス手法をそのまま音に転写したような強度を持つ。

ブラジルのパーカッショニストDom Um Romaoが1976年に発表したラテン・ジャズ/フュージョンの傑作『Hotmosphere』。 豊穣なパーカッションとエレクトリック・ピアノやフルート、ギターなどの緻密なアレンジが織りなすスムースなグルーヴに、MPBやボサノヴァの要素が融合、収録曲もミルトン・ナシメントやアントニオ・カルロス・ジョビンの楽曲がカバーされており、ブラジル音楽への敬意が感じられる内容となっている。都会的なムードと自然の息吹が共存する中、Romaoのパーカッションは単なるリズムではなく、メロディや空間を彩る主役として機能しており、ジャズ・クラブでもビーチでも似合うような、柔らかくも刺激的な音楽性が魅力的。 ブラジル音楽の深みとジャズの自由さが融合した、心地よくも濃密なアルバム。

1968年にジャマイカの〈Merritone〉からリリースされた、ロックステディ黄金期を象徴するインスト名盤。ピアニスト Gladstone “Gladdy” Anderson と、ロックステディのギター・レジェンド Lynn Taitt を中心として、バックは名門バンド The Jets が担当。スカより遅く、レゲエより軽やか、メロディアスで甘いロックステディの柔らかいグルーヴ。Gladdy の優しいピアノと、Lynn Taitt の繊細なカッティングとメロディが溶け合い、ロックステディの甘さ・優しさ・切なさを凝縮している。当時のジャマイカの空気をそのまま閉じ込めたような一枚。

イタリアのライブラリー音楽やサウンドトラック文化を現代的に再解釈するプロジェクト Complesso Gisteri による、架空の美術展をテーマにしたコンセプチュアルなアルバム『Mostra Collettiva』。60〜70年代イタリア映画の音楽や色彩感覚と、現代エクスペリメンタルの静謐な空気が交差し、美術展の展示空間を歩くように音とイメージが立ち上がっては消えていく独特の世界観を描き出す。ジャズ、ラウンジ、サイケ、アンビエント、イタリアン・ライブラリー音楽が自然に溶け合い、エレクトリックピアノやサイケデリックなギターが柔らかく揺らめく。アーカイヴ精神と、現代的な音響センスが絶妙に融合した本作は、洗練されていながら、どこか奇妙でサイケデリック。聴く美術展と呼びたくなるほど視覚的な喚起力があり、アート作品のようにじっくり味わえる、イタリアン・モダン・ライブラリーの新たな名品。

NEU!解散後にKlaus Dingerが結成したLa Dusseldorfによる、1978年リリースの2ndアルバム『Viva』。Dingerの代名詞であるモーターリックで直進的なビートが全編を貫き、シンセとギターのレイヤーが広がりを描きながら、都市的でクリアなを作り上げている。ミニマルな反復の中に祝祭感が宿る15分超の壮大なアンセム「Cha Cha 2000」をはじめ、Neu! よりもポップで開放的なムードが際立っており、クラウトロックの実験性と、ロックの普遍的な高揚感が絶妙に交差する、時代を超えて輝き続ける一枚。


ブラジル出身の名ギタリストFabiano Do Nascimentoと、トロンボーン奏者Vittor Santos率いる16人編成オーケストラによるアルバム『Vila』。リオのスタジオで録音された本作は、Fabianoの指弾きによる繊細なフレーズと、オーケストラの豊かな響きが溶け合うシネマティックなブラジリアン・ジャズ。Fabianoのギターは常に語り手として中心にあり、オーケストラと対話するように旋律を紡いでいく。サンバ・ジャズ、ショーロ、ボサノヴァの伝統を軸にしながら、スケール感と情景を想像させるようなムードに満ちた、現代ブラジル音楽の洗練と、伝統の深みが見事に融合した上質な一枚。


4月上旬再入荷。〈Melody As Truth〉主宰として、そしてGaussian Curveのメンバーとしてアンビエント、バレアリックの現在を形作ってきたJonny Nashが、より内省的な領域へと踏み込んだアルバム『Point of Entry』。柔らかなギターのアルペジオと淡いシンセのレイヤーが静かに呼吸し、音が空気そのもののように空間へ溶けていく。バレアリックの開放感と、室内楽のような親密さが同時に漂う。Joseph Shabason のサックスが差し込む瞬間も美しく、アンビエントの透明感に人肌の温度が重なる。Nashの音楽が持つ静けさの深さを純度高く感じられる、静かに内側へ向かうアンビエント・フォーク。

スイスの新興レーベル〈Fabrique d’Instruments〉から、現代音楽の最前線で活動する謎めいたデュオ、Anichy & Lyemnによるデビュー作。長く引き延ばされた旋律、消え入りそうな弦楽器の響き、遠くから聞こえる音色、そして使い古されたメロディの断片が焦点の中に入っては消えていき、聴くというより思い出す感覚に近い音世界を形づくる。その佇まいは、William Basinski『Disintegration Loops』や、The Caretaker、Gavin Bryarsを思わせるもので、極限まで削ぎ落とされた電子音、ゆっくりと変化する和声、カノン、反復するフレーズが、時間を緩やかに侵食する。ミニマルでありながら、同時にむしろ人肌の温度を感じるような柔らかさも漂い、微細な揺らぎや、遅れて入る声部の感情の余韻に耳を澄ませることで、音の奥に潜む情緒が静かに立ち上がる。


アンゴラ音楽の黄金期である、70年代のギター音楽セムバのスタイルを継承、忠実に再現するConjunto Angola 70と、現代セムバを代表するシンガーPaulo Floresが手を組んだプロジェクトTurma da Bênção。ギター・アンサンブルや軽やかなパーカッション、コーラスの掛け合いといった伝統的なセムバの魅力を、Floresの深みのある歌声が現代的な感性とともに結び直す、世代横断の音楽的対話。録音は生々しく、ギターの指のノイズやコーラスの息づかいまで感じられる現場の空気が魅力的で、磨きすぎない質感が、かつてのセムバの手触りをそのまま蘇らせている。伝統と現代性が自然に溶け合い、アンゴラ音楽ならではの祝祭と郷愁が豊かに息づく一枚。