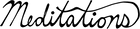RECOMMENDED
121 products


フランス・パリを拠点に活動する、ジャンルの境界を超えた音響探求者であり、クラブと瞑想空間の両方に響く音楽を生み出す稀有な存在Đ.K.ことDang-Khoa Chauによる深遠なダブ・テクノとトライバル・ステッパーズが交錯する実験的クラブ・トラック集『Realm Of Symbols』。これまで〈Antinote〉や〈Good Morning Tapes〉などでアンビエント/ダウンテンポを展開してきたĐ.K.が、本作ではよりフロア志向のパーカッシブなグルーヴへと舵を切り、幽玄な電子音響と東南アジア的な打楽器のニュアンスを融合。Al Woottonの〈Trule〉レーベルらしい、ミニマルでありながら肉体的な強度を持つサウンドは、MuslimgauzeやShackleton、Raimeらの系譜に連なるもので、クラブでもヘッドフォンでも深い没入を誘う。ダークでスモーキーな音像、ポリリズムと空間性が交錯する現代ダブ・テクノの最前線を提示する、Đ.K.の新たなフェーズを象徴する一枚。


アメリカの作曲家・ピアニスト Ruth Maine によるデビュー・アルバム『Found Keys』。20年以上の演奏・作曲のキャリアを持つ彼女が、初めて自身の作品を録音・公開することを決意した非常にパーソナルなアルバムであり、静けさと親密さに満ちた16曲の短いピアノ作品が収録されている。ピアノの旋律はシンプルながらも反復を通じて微細に変化し、各曲は2〜3分ほどの長さでありながらも深みを持ち、自然に囲まれた環境で録音されたことによって環境音や空間の響きが自然に取り込まれていることも相まって、アンビエント、ネオクラシカルの要素が溶け合った音響世界が展開されている。時代を超越したような穏やかさと、古くからの友人のような温もりを感じさせる、音楽というよりも、記憶や感情の断片をそっと鍵盤に乗せたようなスケッチ集。静かな時間に寄り添う一枚として、深く心に響く作品。


「ホーム・ビフォア・ダーク」はエム・レコードの再発で知った大好きな曲。この曲を、大好きなバンドゑでぃまぁこんがカバーしたら最高だろうな、と思っていたらやはり最高!夢が叶いました。」(坂本慎太郎)
ゑでぃまぁこんが、ノラ・ガスリーの名曲を、坂本慎太郎とゑでゐ鼓雨磨の共作オリジナル日本語詞でカヴァーした、良き出会いの繋がりが生んだ二重三重の夢の結晶。トルソ(TORSO)によるドリーミー管弦楽リコンポジション版をカップリングした夢のWサイダー。(ポップスの神様はまだ日本にいらっしゃいました。)
ノラ・ガスリーのたった1枚のシングル「Emily’s Illness c/w Home BeforeDark」(1967年)は、2009年の復刻リリース以来、マニアの秘匿曲を越えて内外に拡がりました。当初は、19世紀アール・ヌーヴォー的耽美をビーチボーイズ『Pet Sounds』風のサウンドで綴った美しい奇曲「Emily’s Ilness」推しだったのですが(※1)、しだいにB面曲「ホーム・ビフォア・ダーク」がミュージシャン達を魅了しはじめ(※2)、伝えられるところではエゴラッピン、ティーンネイジ・ファンクラブ、テニスコーツ & yumboがライブで取り上げて流布していった模様。しかし、まさかこのような予想もしない素晴らしい録音に出会えるとは!!本作は、もともと坂本慎太郎の発案で、ゑでぃまぁこんバンドでプライヴェート録音したもの(同氏の「P」審美眼にリスペクト)。公開目的ではなかったこの隠密録音の噂がエムに届き、長きにわたる円(縁)のループが繋がったような作品をお届けすることになりました。装丁画はゑでゐ鼓雨磨。
=カップリング曲秘話=
カップリング曲の制作は元曲を知らないトルソに打診し、ゑでぃまぁこん版のヴォーカルと旋律楽器パートを抜いたベーシックトラックを渡して、ほとんど目隠し状態でのリコンポジションを依頼(制作中はググり禁止)。当初はシンプルにOrieとKenjiの演奏を被せた合奏で……という趣旨でしたが、この無茶な実験要求に応えたトルソは、最終的にベーシックトラックをも抜きとった叛逆的かつ優雅なリコンポジションを送りつけてきて、このオリジナル曲の出来栄えに一同平伏!
注釈:
1)「Emily’s Illness」は、19世紀アメリカの詩人、エミリー・ディキンソンへのトリビュートと思われる。
2)ガスリーと作者エリック・アイズナーは当時アストラッド・ジルベルトの大ファンだった。初期アストラッドのたどたどしいボサノヴァ歌唱とノラの歌う「Home Before Dark」を頭の中でダブらせて再生してみてほしい。
=作品仕様=
+ 3 面折り込みジャケット
+ 歌詞掲載
TRACKS:
Side A - ホーム・ビフォア・ダーク
Side B - ホーム・ビフォア・ダーク(Recomposed by TORSO)


日本人の母を持つ、ミシガン州アナーバー出身、ニューヨーク・ブルックリン拠点の女性ギタリスト/シンガーソングライターであり、ジャズやブラジル音楽、J-Popなど多様な影響源を独自の音楽世界に落とし込んできたMei Semonesによる感情豊かな2曲入りの7インチ・シングル『Kurayami / Get used to it』。ミシガンでの青春と喪失を描いた、変拍子と技巧的ギターが光るエモーショナルな楽曲「Kurayami」と、孤独の美しさをテーマにした、ジャズ・トリオ編成による繊細で温かなバラード「Get used to it」を収録。


そのスタイリッシュで風雅なハウス・ミュージック・プロダクションで世界的によく知られているだけでなく、ビデオゲーム・サウンドトラック制作も数多く手掛けるジャパニーズ・ディープ・ハウス・レジェンド、寺田創一。その世界的な再評価のきっかけとなった1990年代から2000年代初頭にかけて自身のレーベル〈Far East Recording〉からリリースされた作品をHuneeのキュレーションでまとめた〈Rush Hour〉からの画期的編集盤『Sounds From The Far East』が、日本語帯とインナースリーヴが付属して2025年エディションとしてリイシュー。自身による名曲の数々だけでなく、Shinichiro YokotaやManabu Nagayamaといった盟友プロデューサーたちの非常に人気溢れるトラックの数々を満載した格好の2LP!90年代初期の米国のディープ・ハウスに大きく影響を受けた〈Far East Recording〉のサウンドを堪能するのにピッタリな一枚です。寺田とNami Shimadaによる、パラダイス・ガラージの素晴らしい名曲"Sunshower"をベースにしたトラック"Sun Showered"も収録。初リリース時、日本産ハウス再評価の決定的契機となったもので、サンプリングとエレクトロニクスを駆使したオールドスクール・ハウスでありながら、現代的な感覚でも楽しめる名盤。

パンクの衝動を文学の鋭さで昇華させた90年代日本ロックの隠れた金字塔!邦楽史を代表するパンクの枠を超えた伝説、現在は町田康として武蔵野大学文学部教授でもあり小説家として著名な町田町蔵が1992年にリリースした『Harafuri』。INU解散から11年後に生まれたこの作品は、80年代初頭のパンク直撃の勢いとはまた違い、文学的な成熟と毒気を帯びた歌詞を、北澤組の重厚かつモダンなバンドサウンドに乗せたもの。INU『メシ喰うな!』の頃から町田はすでに「詩人がロックをやっている」ような存在だったが、『Harafuri』ではその言葉の鋭さや比喩の豊かさがさらに深まり、社会風刺や日常の不条理をえぐるような表現が際立っている。北澤組のサウンドはハードでタイト、当時のオルタナティヴ・ロックやポストパンクの感触もあり、町田の言葉を受け止める強度を持っていた。今回は初の公式リイシューで、音源のリマスターはもちろん、歌詞の英訳も丁寧にやり直されており、町田のユーモアと皮肉を含んだ言葉遊びを国際的なリスナーにも開く試みになっている。


90年代ポストロックの代名詞としてシカゴから世界を震撼させた世界最高峰のインストゥルメンタル・バンド、Tortoise。『Millions Now Living Will Never Die』や『TNT』といった歴史的名盤で築いた唯一無二の音響建築は、今も多くのジャンルを越えて影響を与え続けています。そんな彼らが9年ぶりに放つ最新作『Touch』は、地理的に散らばったメンバーがロサンゼルスやポートランド、シカゴを行き来しながら制作したアルバム。プロセスは変化しつつも、その音楽はむしろ過去以上に有機的で、深く結びついていると感じられます。緻密に重ねられたリズムとマレットの揺らぎ、ギターとシンセの多層的な響きが織りなすのは、都市の夜景や見えない物語を想起させるシネマティックな音像。混迷の時代にあっても「人は適応する」と語る彼らの姿勢が、そのまま音に刻まれたような傑作です。MUST!!!!

テクノとダブ・レゲエの奇跡的合一。オリジナルは2001年に発表されていたRhythm & Soundのカタログ5番が待望の2025年リプレス!独Mark Ernestus & Moritz von OswaldのBasic Channelによる、唯一無二な孤高の音響空間。


Aesop RockことIan Bavitzによる、セルフプロデュースによる内省的かつ開かれたサウンドが特徴のヒップホップ作品『I Heard It’s A Mess There Too』が〈Rhymesayers Entertainment〉より登場。全曲のプロデュース、作詞、パフォーマンスを自身で手がけ、複雑で詩的なリリックは健在で、ビートの余白が言葉の密度を際立たせる設計となっている。明瞭なビートとファンク要素が導入されており、言葉の密度とリズムの余白が絶妙に絡み合い、リスナーに深い読解と反復を促す。抽象性と技術的精緻さが融合した言葉の迷宮のような一枚。「Poly Cotton Blend」や「Sherbert」など、ファンから高評価を受けるトラックも多数収録。

NEU!解散後にKlaus Dingerが結成したLa Dusseldorfによる、クラウトロックの実験性をポップに昇華させたデビュー作。収録曲「La Düsseldorf」「Silver Cloud」「Time」は、反復するモータリック・ビートとシンセの煌めきによって、催眠的かつ祝祭的な空気を生み出しており、Klaus Dingerのエネルギッシュなヴォーカルとミニマルな構成の中に広がる開放感が印象的。ジャーマン・ロックの枠を越えたジャンル横断的な魅力を放ち、アートロック的な視点とDIY精神が融合したこのアルバムは、後のニューウェーブやテクノにも影響を与えた本作は、クラウトロックの進化を象徴する一枚として、今なお新鮮な輝きを放ち続けている。


2023年にリリースした空間現代のアルバム『Tracks』のリミックス盤をリリースします。
ジューク/フットワークのDJ「D.J.Fulltono」、WIREのベストにも選出された日本の新鋭DUBプロデューサー「Element」、ヒップホップグループMoe and ghostsのトラックメイカー友人カ仏、コンピューターミュージックの巨匠「Carl Stone」、Honest Jon'sやDDS、Sahkoなどから作品を発表するNYの鬼才「MADTEO」のリミックスをそれぞれ収録しています。レコードに付属のダウンロードコードからダウンロードいただくと、更に2曲ボーナス・リミックスをお聴きいただけます。
1. D.J.Fulltono - Burst Policy (remix)
2. Element - Look at Right Hand (remix)
3. 友人カ仏 from Moe and ghosts - Beacons (remix)
4. Carl Stone - Fever was Good (remix)
5. Madteo - Hatsuentou (remix)
Digital Mastered by Tatsuki Masuko
Vinal Mastering and Cutting by Atsushi Yamane


青木孝允とツジコ・ノリコによるオリジナルは2005年リリースのコラボ・アルバム『28』。3年以上にわたる遠隔制作を経て完成した東京とパリをつなぐ音の往復書簡のような本作は、甘美な浮遊感のある日本語ボーカルと繊細なエレクトロニクス、ファンキーなビートが有機的に融合し、BjörkやMatmosを彷彿とさせる実験性とポップ感の絶妙なバランスの音響世界を展開。歌と電子音が対話するような構成で、親密さと距離感が同居する。クラシックなエレクトロニカの質感と、揺らぎのあるテクスチャーが心地よい、静かで夢見心地なアートポップの逸品。時代を経て聴くたびに新しい表情を見せる、繊細で私的な相思相愛の名コラボレーション。

〈Paradise Is A Frequency〉が手がける初のコンピレーション『The Style of Life』は、70分にわたる頭の中のバカンスとも言うべき奇妙なセレクション。中古レコード屋やネットの片隅から発掘された、スムースジャズやVHSワークアウト音源、イージーリスニングのカセットテープといった、忘れ去られたフォーマットが素材になっている。メタモルフォシス、ロラッド・グループ、スキー・ジョンソン、メンサーらの楽曲が並び、軽やかでどこかチープな快楽感に満ちている。作品全体は90年代あたりにあった自己啓発や企業向け啓蒙ビデオ、あるいは健康・フィットネス VHSなどを思わせる作りになっており、音だけでなく付属のブックレットも含めて、架空の企業が描く「理想の生活」をパロディ化したような世界観に浸れるようになっている。ヴェイパーウェイヴ以後の感性で再発見されたスムース・ジャズ、ニューエイジ断片集と言った趣きの、リスナーを日常からずらしてくれる、奇妙に懐かしく、そしてどこかくすっとさせてくれるユーモラスな作品。


1970年代末から交流を持ち、ポストパンク/アヴァン・ポップの文脈で活動してきた音楽家同士であるPeter Gordon(Love of Life Orchestra)とDavid Cunningham(Flying Lizards)による、ポストモダンな実験精神とポップの遊び心が交錯する、ユニークな音響作品『The Yellow Box』。本作は、サックス、フィールドレコーディング、電子音、語りなどが交錯する多層的な音響構造とともに彼らの過去の断片的なアイデアや未発表素材を再構成したコラージュ的アルバムであり、脱構築的なリズム、再配置されたメロディ、そしてユーモアを帯びた音響実験が展開される。各トラックは1〜5分程度の短編で構成されており、断片的ながらも全体としてひとつの箱庭的世界を形成している。タイトル『The Yellow Box』が示すように、本作は“箱”というメタファーを通じて、音の収集・分類・提示という行為そのものを問い直す作品でもあり、この箱を開けることで、ポップと実験、過去と現在、構造と偶然が交錯する音響の迷宮へと誘われるような一枚。


日本のギタリスト本多信介が1991年にCDで発表したアンビエント・ジャズの名盤『晩夏』が〈Studio Mule〉より2LP仕様で再発。本多信介は伝説的バンド、はちみつぱいのギタリストとして知られ、その後ソロでアンビエント・ジャズを探求。繊細なギターのアルペジオに、クラシカルな響きやジャズ的即興が交錯する、タイトル通り「晩夏」の情緒を感じさせる、叙情的で瞑想的なサウンド。日本のアンビエント・ジャズ史における隠れた傑作でありながら、坂本龍一や細野晴臣らの流れと並ぶ独自の美学を提示した作品として再評価の進む一枚。

アムステルダム出身、現在はハーグを拠点に活動するKim David Botsによる『Instrumental Romance』。日常の断片や記憶を詩的に描写するスポークンワーズ的な語りと、アナログ感のあるシンセ、ギター、フィールド録音などが混ざり合うローファイで親密なサウンドが温かくも不思議な音世界を構築。オランダ・マース川沿いの古びた農家で暮らしながら制作し、毎朝6時に犬のMiemelと川辺を散歩。霧の中でコーヒーを飲むという日課が作品の詩的世界に反映されている。皮肉やユーモアがありつつも、どこか切ない雰囲気が漂うバランスが絶妙で、静かな時間にじっくり聴くことで、日常の中に潜む物語や感情が浮かび上がってくるような魅力のあるアルバム。


ベルギーの音楽家Hieleによるレフトフィールド・エレクトロニクス、IDM、ニューエイジな要素が混ざり合ったアルバム『Emo Inhaler』。レトロなシンセサイザーの音色、遊び心のあるメロディ、深みのあるテクスチャと不規則で複雑なリズムが印象的な本作は、複数のスタジオや列車のコンパートメントで録音。断片をつなぎ合わせたような、奇妙な楽しさと、どこか懐かしいメランコリーが交錯する無邪気で不可思議な音響空間。視覚芸術家や映像作家とのコラボレーション経験を活かした空間や映像と結びつくような映画音楽的な感性と、どこかズレたポップ性を併せ持っている。「感情の吸入器」というタイトル通り、感情の断片を音で吸い込むような夢幻的な作品。


アメリカのアヴァンロック・カルテットHorse Lordsと、ミニマル音楽の重鎮Arnold Dreyblattによる、〈RVNG Intl.〉の世代を超えた音楽家によるコラボレーションをテーマとしたFRKWYSシリーズ第18弾『FRKWYS Vol. 18: Extended Field』。Dreyblattが長年探求してきた純正律とHorse Lordsのポリリズミックで実験的な演奏スタイルが融合し、緻密でありながら身体的なグルーヴを持った作品となっており、金属製ダブルベースの弓奏、変則チューニングのギター、複雑なドラムパターンが交錯する。Dreyblattの緻密な音響とHorse Lordsのライブ感、ミニマリズムが持つ理論的な厳密さとアヴァンロックの肉体的強度、Horse Lordsの複雑なリズム構造とミニマリズムの反復美学という、ミニマリズムとアヴァンロックの新たな接点を提示しており、考えながら踊るような、知的でありながら感覚的にも深く響く一枚となっている。


Jesse Sykes & The Sweet Hereafter による2011年の『Marble Son』以来となる実に14年ぶりの新作『Forever, I’ve Been Being Born』。前作発表後にリズム隊を失った喪失感や、音楽から距離を置かざるを得なかった状況を背景として、10年の歳月をかけて制作された本作は、フォークを基盤にブルースやサイケデリック、オーケストラルな響きが溶け合う、深い陰影を持った作品になっている。ハスキーでありながら透明感を保ち、年齢を重ねた分だけ一層親密で深い響きを帯びたジェシー・サイクスの声を中心にして、ギタリストのフィル・ワンドシャーはその声を縁取るように、時にクラシックな、時にざらついたトーンで対話を重ねる。タイトルが示すとおり生命の循環と向き合っており、ジェシー自身が「弔辞のように感じる」と語るように、全体が静かな受容と祈りのトーンに貫かれている。哀愁を帯びたメロディーと、深く感情的な歌詞、暗くも透明な歌声が時に鎮魂歌のように響く、聴き手を深く包み込む作品。

絵画、彫刻、音響、映像などを横断する作品で知られる世界的な現代芸術家、Anne Imhofによる、エクスペリメンタルな音響作品『WYWG』が大名門〈PAN〉より登場。本作は、彼女が2001〜03年に録音・撮影した個人的な映像や音声素材をもとに、それらを現在の視点から再編集し、アート作品として再提示したもので、従来の楽曲構造にとらわれない、アンビエント、エレクトロニック、インダストリアル、ポストクラブ的要素を融合し、緊張感と静寂が交錯するサウンドが特徴的。イムホフ自身に加え、イライザ・ダグラスやビリー・ブルシールなども制作に参加し、彼女のパフォーマンス作品で構築される、緊張感と無気力感が入り混じったような世界観を音で再現している。即興性と身体性を重視した録音で、Imhof自身の声やギターも用いられ、パフォーマンスや共同体的な空気と密接に結びついた音響表現となっている。48ページのアート・ブックレットが付属するなど、単なる音楽作品ではなく、彼女のアートを体現する総合的なインスタレーションというべき一作。


1月中旬再入荷。Joshua FrankとTom Ngからなる2人組であり、北京の現行地下を大いに盛り立てる尖鋭的デュオGong Gong Gong 工工工と、台湾を代表する現行サイケデリック・バンドMong Tong。それぞれ独自のミニマルかつシネマティックな音を鳴らしてきた2組のデュオが合流して作り上げた架空のカンフー映画のサウンドトラック『Mongkok Duel 旺角龍虎鬥』。Gong Gong Gongによる「Rhythm n’ Drone」的な反復と緊張感に、Mong Tongならではの怪しげなエフェクト処理やサイケデリックな質感が重なり、サイケ・ドローンとグルーヴィーなベースリフ、荒々しいギターが入り乱れる。モーターリックなリズムを基盤に、繰り返しの中でじわじわと景色が変わっていく感覚は、まさに幻の武侠映画のサウンドを思わせる。レコーディングは香港・旺角の老舗スタジオ President Piano Co. のリハーサルルームで行われ、そこで1978年創業当時から残るアンプや楽器を使用。さらにスタジオのオーナー、李景一による独自の録音システムを通したことで、荒々しいのに妙に鮮明なヴィンテージ感が生まれている。アジアの都市の熱気と幻覚的なサウンドイメージが交錯する、不穏でいて痛快な一枚。

2020年にレースカットLPで限定50部のみ流通したCindy Leeによる秘蔵アルバム『Cat O' Nine Tails』が、〈W.25TH〉より待望の再発。『What’s Tonight to Eternity』録音直後に制作され、後の『Diamond Jubilee』に繋がる、クラシックなソングライティングとクラシカルな構成美が共存した傑作としてコアなファンの間で語り継がれてきた。アルバムは、ゴシック調の「Our Lady Of Sorrows」から幕を開け、タイトル曲の躁的なエクスペリメンタル、そしてウェスタン映画のような「Faith Restored」へと展開。映画のサントラのような構成で、特に「Love Remains」は、フリーゲルの繊細で痛々しいヴォーカルが映える感傷的なバラードで、アルバムの感情的なハイライトになっている。後半ではライヴの定番エンディング「Cat O’ Nine Tails III」、そこから名曲「I Don’t Want To Fall In Love Again」へ。親密さと異質さが絶妙に同居した一曲。ラストの「Bondage Of The Mind」まで、Cindy Leeの重要な進化の過程を刻んだような全9曲が並んでいる。ゴシック、ウェスタン、ソウル、実験音楽が溶けあう、心の奥を揺らす、「もうひとつの」60年代映画サントラ!


オリジナルは15年に〈CCQSK Records〉よりプライベート・エディションのLPとしてリリースしていた傑作が〈Superior Viaduct〉傘下の〈W.25TH〉よりアナログ復刻!ゼロ年代後半に圧倒的人気を誇ったものの、ギタリストのChristopher Reimerの突然の死によって解散することとなってしまった現代カルガリーの伝説的ノイズ・ロック・バンド、”Women”(当時私も大好きでした...!!)のリード・シンガー、Patrick
Flegelが展開してきたソロ・プロジェクト、Cindy Leeの初期作『Act Of Tenderness』!まさにカタルシス。今は去りし全盛期のローファイ・インディ/ドリーム・ポップへの憧憬、陰鬱と寂寞と不可解・・・在りし日のWomenを思い出すローファイ/ドリーム・ポップ"What I Need"を始め、This Mortal Coil~Cocteau Twinsといった〈4AD〉直系のイーサリアルな世界観とインダストリアル・グラインドが溶け合っていく異形の音像"New Romance"、フィードバックする金切り声、エクストリームなノイズの衝動へとどこまでも駆られる"Bonsai Dream"など、マスターピース満載の傑作ファーストLP!ぜひご体感ください。