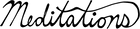MUSIC
6071 products


〈Ninja Tune〉傘下のレーベル〈Technicolour〉から世界が注目するインストバンド、ユーフ。近年、東洋と西洋を掛け合わせた摩訶不思議な音楽で人気を博すグラス・ビームスを輩出した〈Ninja Tune〉の今の方向性の一つを示すように、世界各地の音楽からの影響を融合した唯一無二のサウンドで熱い注目を集めている彼らが、最新EP『Mt. Sava』をリリース!
2025年初頭に発表されたEP『Alma’s Cove』に続く本作は、バンド自身が「精神的な姉妹作」と語るように、前作の穏やかな海辺から舞台を移し、雄大な山岳砂漠のスケールを描く自然の音風景と静かな内省を描いた6曲を収録している。
先行シングル「Mesa Mesa」は、砂漠に広がる壮大なテーブルマウンテンへのオマージュで、Mdou MoctarからLed ZeppelinやBlack Sabbathまで幅広い影響を感じさせ、これまでの幻想的なサウンドを損なうことなく、よりヘヴィなサウンドを取り入れている。
EP『Mt. Sava』では、全6曲を通じて広大な景色がさらに広がっていく。オープニングの「Moon Dive」は、夜明けを迎える静かなひとときを瞑想的に描き、聴き手に休息と内省の空間を提供する。一方、「Night Air」では山岳地帯特有の気温や湿度の変化に触発され、夜の砂漠の脈動を表現。「山岳砂漠の環境では昼夜の温度・湿度の変化がより強く感じられる」とバンドは語っている。
デンマーク語で砂漠を意味する「Orken Bloom」は、日の出を映し出すようなダイナミックでスピード感のあるトラック。さらに「Calima」では、サハラの砂を大陸を越えて運ぶ風に着想を得て、静けさのひとときを描き出している。


(数量限定/日本語帯付き/解説書封入)キャリア屈指の人気を誇る名曲「Girl/Boy Song」を収録したエイフェックス・ツインの代名詞的作品。
自らの本名を冠し、同名の亡き兄へと捧げられた作品(1996年リリース)。アナログ・シンセからソフトウェア・シンセへと制作機材もシフトし、痙攣するビートにクラシックやトイ・ミュージックを掛け合わせ、無二のポップ・ミュージックへと昇華された90年代を代表するアルバム。ドラマチックにたゆたう弦楽器とエモーショナルにのた打ち回るビートとのコントラストが琴線を直撃する名曲「Girl/Boy Song」は本作に収録。


2008年以来、18年ぶりのヴァイナル・リイシュー。2025年にはEU&USツアーを予定。
(前略)
「頭のなかで完璧なトラックが鳴っているんだ。だけど、それを具体化するのはとても困難なんだ。なぜなら……」
かつてオウテカは言った。「それはつねに変化しているから」
たしかにその通り、彼らのアルバムやシングルはその軌跡なのだろう。オウテカは、いまだ変化するその自らの頭で鳴っている断片をアルバムというカタチで表現しているのだろう。僕は2001年に、『Confield』のライナーノートで、「オウテカは“慣らされてしまったことへの服従”に抵抗する」と記したけれど、もはや“抵抗”どころではない。オウテカはこの15年、あたかも自らの音楽性で自らを隔離=『Quaristice』するかのような栄誉ある孤独を選び、彼らの芸術性を完璧なまでに世間に認めさせたのだ。リスナーに評価されるのではなく、リスナーの耳をテストすると喩えられるところまでいったわけだ。(中略) ショーンは『Quaristice』というタイトルに意味はないと言うけれど、しかし多くの人は考えてしまうだろう。この音世界はダンスフロアからもサイケデリックからも、あるいは現代音楽からも“隔離”されていると。
「“現在”にいることが重要だと気付いたんだ」ショーンは言う。「聴き直したり、昔の音源を聴いてそれについて
考えたりはいっさいしない。だって20年前の自分がどんな人間だったかも覚えてないんだから!」
オウテカらしい、素晴らしい言葉じゃないか。
野田努 (Quaristice国内盤ライナーノーツより一部抜粋)

〈Organic Music〉や〈Revelation Time〉などと並んで国内からオブスキュア以降のリバイバルを牽引した名レコード店〈ONDAS〉運営でも知られる、日本屈指のレコード・ディガーことDubbyと〈Rush Hour〉のボスAntalが共同で編纂した、新時代に向けた日本のテクノ・ポップのショーケース・アルバム『TECHNO KAYŌ VOL. 1 - JAPANESE TECHNO POP 1981 - 1989』が堂々リリース!SHOGUNへの参加も知られる名アーティスト・大谷和夫の手掛けたオブスキュアな映画サントラ『恋子の毎日』収録のネオ・クラシカル/ミュータント・ファンクな「ラスト・バトル」、近年人気再燃する大名盤『KOIZUMI IN THE HOUSE』からの小泉今日子によるバレアリック・ハウス聖典「マイクロWave」にいたるまで、ポスト・バレアリックやオブスキュア・シティポップ視点を巧みに交差させながら、2025年の現在地点における、ディープな国産テクノ・ポップの数々を寄りすぐった画期的コンピレーション・アルバム!


日本の伝説的アーティスト、Susumu Yokotaの音楽的探求の軌跡を年代を超えて記録した、極めて個人的な作品集『Image 1983-1998』。本作は、彼の音楽キャリアにおける二つの異なる時期に制作された短い楽曲で構成されており、前半のトラックは1983年から84年にかけての、ギターやオルガンを用いたローファイなテープ実験の時代のものが収録、ポストパンクやゴーストリー・ポップの断片が垣間見える。続く後半のトラックは、これらの初期作品に触発され1997年から98年に作曲されたもので、後のアンビエントの傑作『Sakura』へと繋がる、より洗練された電子音響とメロディと抽象性が両立する作品が収録されている。音楽的自伝ともいうべき内容で、初期の脆いギターの音色と、後年の穏やかなシンセサイザーのモチーフが、アルバム全体を通して「記憶と予感」という共通のムードで結びついており、両時代が並行して存在するような不思議な感覚を覚える。彼がテクノの制作で多忙を極める中で、初期の実験への回帰と感情的なミニマリズムを追求した、音のスクラップブックあるいはデザインボードとも呼べる、アーティストの核心に迫る貴重なドキュメント。


Laura Mulvey & Peter Wollen監督による1977年のフェミニスト映画のために制作されたサウンドトラックで、Mike RatledgeがARP、Moog、VCS-AKSなどのアナログ・シンセを駆使して作り上げた、サイケデリックかつミニマルな電子音楽作品『Riddles of the Sphinx』。元Soft Machineのキーボード奏者として知られるRatledgeが、ARPやMoog、VCS-AKSなどのアナログ・シンセを駆使して構築。映画と音楽の融合を支えたアンダーグラウンド文化のキーパーソンDenys Irvingが開発・改造したZ-80ベースのシーケンサーを用いたねじれたメロディと浮遊する音響処理は、映像のパンやモノローグと呼応しながら、空間的で抽象的な音の連なりを生み出している。Boards of Canadaの原型とも評されるその音像は、タイムレスで神秘的な質感を持ち、Terry RileyやMorton Subotnick、Shackletonなどのファンにも響く内容。オリジナル・マスターテープが失われたという背景もあり、幻の電子音響作品として再評価され、映画の文脈を超えて現代のリスナーにも届く一枚となっている。
![I-TIST x TOROKI - TOROKI x I-TIST [Chemistry / Temple Runner] (12")](http://meditations.jp/cdn/shop/files/a1286479905_10_{width}x.jpg?v=1761561334)
![I-TIST x TOROKI - TOROKI x I-TIST [Chemistry / Temple Runner] (12")](http://meditations.jp/cdn/shop/files/0039172260_10_{width}x.jpg?v=1761561334)
フランスのアンダーグラウンド・ダブ・プロデューサーI-TISTと、ドイツ・ミュンヘンを拠点に活動するTOROKIによる初のコラボレーションEP『TOROKI x I-TIST – Chemistry / Temple Runner (12")』。本作は、2022年のボルドーでのDub Schoolセッションをきっかけに制作され、BPM150前後の高速ステッパーズを軸に、重厚なサブベース、トランシーなシンセ、インダストリアルなダブ処理が炸裂する4トラックを収録。チルアウトとトランスの境界を曖昧にしながら、サウンドシステム向けの爆音仕様でクラブや野外フェスでも圧倒的な存在感を放つ。MAD PROFESSORやRHYTHM & SOUND、ZION TRAINなどのファンにも響く、現代ダブのエネルギーと実験性が凝縮されたデンジャラスな一枚。


スウェーデン人プロデューサー、Henrik JonssonがPorn Sword Tobacco (PST)として名を馳せる以前、Stress Assassin名義で2002年にCDで発表したトランス・ダブの秘宝的名作が、20年以上の時を経て初のヴァイナル・リイシュー。本作は、ヘンリク・ヨンソンがヨーテボリの屋根裏部屋で制作した初期の作品であり、ミニマルなビートとスペーシーなシンセが織りなす音響空間は、アンビエント、ダウンテンポ、トランス、エレクトロニカ、そして深遠なダブの要素が融合し、静謐でありながらエモーショナル。チルアウトとトランスの境界を曖昧にするような深い没入感と浮遊感のなか、メロディアスなベースラインと、澄み切った透明度の高いハーモニーを基調としつつ、フィールドレコーディングされた音やテープヒス、浮遊する声などが混じり合う。Harold BuddやTangerine Dreamからの影響を感じさせつつも、Lee "Scratch" PerryやMoritz von Oswaldといったダブの巨匠たちからの手引きも見受けられ、スモーキーで優美なビートと空間を漂うような音響処理が織りなすサウンドスケープは、まるで夢の中で聴くダブ・ミュージックのよう。2000年代初頭のスウェーデン地下シーンから生まれたこの作品は、今なお色褪せることのない、アンビエント/ダブ/エレクトロニカの交差点に立つ静かな金字塔!


エストニア・タリンを拠点に活動し、レフトフィールド・ハウスやアンダーグラウンド・クラブ・ミュージックの文脈で知られるDJ、音楽家のRobert Nikolajevによる限定150部のLP作品『Transplant Rejection』がウクライナのレーベル〈Muscut〉から登場。本作ではクラブ志向とは異なるローファイで粒状の質感とセピア調のノスタルジアが印象的な、ダーク・アンビエント/エレクトロニカを展開しており、より個人的で静謐な側面が表れている。音の構成は、ぼやけたシンセのレイヤー、微細なノイズ、断片的なメロディが交錯し、まるで記憶の中の風景を手探りで辿るような感覚を呼び起こす。Nikolajevが丁寧に編み上げる孤独と記憶のための音楽にリズムはほとんど存在せず、時間の流れさえ曖昧になるような構造の中で、聴くものは音の余白に身を委ねる。永遠の冬を予感させる秋のメランコリーを体現したような、内省的で物悲しい雰囲気を持つ、架空のサウンドトラック的な作品集。


Mark FellがExplore Ensembleと共に制作したコンピュータによる構造とアコースティックの融合による緻密で抽象的な室内楽的音響作品『Psychic Resynthesis』が〈Frozen Reeds〉より登場。本作は、Mark Fellがアルゴリズムで生成した楽譜をアンサンブルが演奏するという実験的手法を採用しており、全10曲は「Combination #1〜#10」と題され、それぞれ異なる数値パターンで構成。電子音楽の思考法をアコースティック室内楽に転写する試みであり、その独自の構造によって、電子音響を用いずとも電子音楽的な設計思想が全編に貫かれた内容となっている。各曲は異なるリズムパターンや音の配置によって構成され、弦を弾く音や擦過音、沈黙も交えながら、録音空間の響きも音楽の一部として取り込んでいる。電子音楽特有の精緻なリズム構造に生楽器の持つ微妙なゆらぎやテクスチャが加わった、数学的な決定性と演奏家の柔軟性が拮抗する知的な音響探究!


フリー・インプロヴィゼーション界の伝説的ギタリストDerek Baileyと、数々の〈ECM〉作品に参加しているパーカッショニストのPaul Motianが共演したデュオ・ライブ音源『Duo in Concert』が、Roland KaynのBOXやJulius Eastman作品で知られるフィンランドの前衛レーベル〈Frozen Reeds〉からアナログ・リリース。それぞれ異なった領域での即興演奏の先駆者が1990年代初頭に行った2つのライブ・パフォーマンスを収めた画期的ライブ・アルバム!

フランス出身、ギリシャ在住の異端DJ、OKO DJによる、原始的なDIYテープモンタージュから現代のホームスタジオ技術まで、幅広い手法を用いて、ダウンテンポ、トリップホップ、実験シンセポップ、ダブという多様な要素が混ざり合ったアルバム『As Above, So Below』。スピリチュアルな語り、テープノイズ、フィールド録音的な要素が交錯し、夢幻的なサウンドスケープを構築。トラックには「Exolition」「La Colline au Ciel」「είμαι ή δεν είμαι(feat. onarrivenow)」など、多言語・多文化的なタイトルが並び、地理や時代、ジャンルを越えた感覚を誘う。レーベルによる紹介文では、「コミューン出身の女ゲリラたちがボウリングに行く」という奇妙な物語が語られ、幻想的で詩的なナラティブが音楽と並走しており、〈STROOM〉の共同的な美学とも共鳴して聴き手の想像力を刺激する、聴く体験そのものが拡張されるような詩的でコンセプチュアルなアルバム。

インドネシアのミュージシャン兼プロデューサー、Bambang Pranotoによるプロジェクト、Banjar Teratai Capungによるオリジナルは2003年CDでリリースの静謐なアンビエント傑作『Tunggak Semi』がリマスター、初のヴァイナル・リイシュー!自然への瞑想的なまなざしをテーマに、アコーディオン、アコースティック・ギター、フルート、パーカッションなどを用いた穏やかで詩的なサウンドで、東洋と西洋の記譜法が交差する独自の作曲スタイルで、ジャンルを超えた世界のあいだの世界を描いている。DIY的なスタイルで制作され、物悲しくも懐かしい旋律と自然の美しさと喜びを反映したハーモニーが、深いノスタルジーをもたらす。ドン・チェリーやジョン・ハッセル、モノ・フォンタナなどの精神性とも共鳴する、静かで深い音の旅へと誘割れる一枚。


Pitchforkでは”The Best Experimental Albums”にも選出されるなど、日本から大きな話題を呼んだ作家による2019年発表の2ndアルバムが2025年エディションで待望のリプレスです!
浮世絵や雅楽、そして、宮崎駿からJ Dillaにまでインスパイアされた孤高のエクスペリメンタル・アンビエント大傑作!「lost Japanese mood」をコンセプトに活動する広島在住の日本人作曲家、Meitei / 冥丁。これは本当に美しい・・・・本作は、彼の99歳の祖母の死からインスパイアされており、タイトルは小野小町から取られているとのこと。彼の祖母が生きた古き日本の心象風景を切り取るように、今は失われた日本の原風景を描き出した孤高のアルバム。TempleATS周辺の作家達の才気にも劣らない、国籍すらも遥かに超克し、妖艶にして澱み一つ無い、まさに無比と言えるエキゾティック・アンビエント傑作。鈴木春信によるカバー・アートワークをフィーチャー。Brandon Hocuraによるマスタリング。横田進や竹村延和、吉村弘のファンの方も必携の一枚です!

2021年発表当時はレーベルでも予約時完売だった人気作が待望のリプレスです!先日はSeekersinternationalとも意外なコラボレーションを実現、レイヴ・サウンドからドラムンベース、ダブステップ、フットワーク、ジャングルまでも横断してきたブリストルの名DJ/プロデューサー、Om Unit。〈Planet Mu〉でのMachinedrumとの仕事やD&Bの御大レーベル〈Metalheadz〉、dBridgeの〈xit Records〉など各所から独特の作品をリリースし評価を得た彼の2021年限定自主盤リリース。貫禄の出来といった仕上がりで独自の宇宙観を大発揮。ダブとアシッド、アンビエントを軸に据え、ドップリな303ベースラインを聴かせてくれる傑作盤。


版元完売につきお見逃しなく。名古屋を拠点に活動する音楽家、Shawn Seymourによるユニット、Lullatoneが届けるこのアルバムは、植物をテーマにしたアンビエント・コレクション。日常の中でひっそりと流れる空気のような楽曲群は、儚くも美しい旋律で構成されており、さながら音で綴るボタニカル日記のよう。ギターやトイピアノ、アナログ・シンセやカセット特有のノイズといった要素が、音の一粒一粒を大切に、繊細に編まれており、曲は短く、どれも1~2分程度だが、それがかえって一瞬の美しさを引き立てている。名古屋の花屋「Tumbleweed」で定期開催されているイベント「Flower Listening」のために作られた楽曲を基に構成されており、Shawnはこのイベントのために何曲も書き下ろし、それらが日常の他の場所や時間でもふと寄り添うような音楽へと育っていったという。音の質感はGigi Masinや吉村弘を思わせるが、Lullatoneならではのチャーミングなトーンが全体を包んでおり、シリアスすぎず、全体を通して穏やかな物語のような流れを感じさせる。日記風でもあり、ドリーミーでもある、植物と暮らす日々のための小さなサウンドトラック。


ロンドンを拠点とするコロンビア人アーティスト、OKRAAことJuan Torres Alonsoによる、エレクトロニックを基盤に、アンビエント、ダウンテンポ、ブレイクビーツ、さらにはラテン系の実験的な要素までを広く包含したアルバム『La Gran Corriente』が〈A Strangely Isolated Place〉より登場。多様な要素を取り込みながら、緻密なサウンドデザインによって統合されており、スペイン語で「大いなる流れ」を意味するアルバムのタイトル通りの領域横断的な独自の探究の成果が現れた一枚となっている。Taylor Deupreeがマスタリングを担当するなど、音質へのこだわりも感じられる作品。


ポートランド拠点のサウンド・アーティストwndfrmことTim Westcottによる、マイクロ・リズミックなIDMを探求したアルバム『WVLT』。音を、従来の最小単位である16分音符や32分音符よりもさらに細かい、聴き取れるかどうかの境界線上にある数ミリ秒単位の音の粒子に分解し、それらをランダムまたは緻密に再配置することで、パルス感やザラザラしたテクスチャ感を生み出し、また、完璧なタイミングではなく、意図的に不規則な揺らぎを加えることで、機械的でありながら有機的で複雑なグルーヴを作り出している。リズムは駆動力というよりも「震え、崩壊し、再構築される」ように展開し、緻密なコントロールとそこから逸脱する即興性の絶妙なバランスにより、ミニマルでありながら濃密な音響空間を創出している。〈A Strangely Isolated Place〉らしい、アンビエントとエレクトロニカの間の静謐で緻密な世界観を提示する作品。

アメリカ・ポートランドを拠点とするKevin Hayes、Kirk Marrison、Clark Rehberg IIIによるトリオKILNの〈A Strangely Isolated Place〉から通算8作目となるアルバム『Lemon Borealis』。彼らの30年以上にわたる長きにわたる活動の集大成であり、アンビエント、エレクトロニカ、IDM、ダウンテンポの境界に位置する独自の音世界を展開。ライヴ・パフォーマンスによる即興性の高い演奏、緻密なビートメイキング、音の波形そのものを細かく加工・変形して、独自の音色やテクスチャを創り出す複雑な音響効果を凝縮し、有機的なテクスチャ、微妙なメランコリー、鮮やかなリズムを織り交ぜた、色彩豊かで没入感のあるサウンドスケープを提示している。ハイ・ファイとローファイの境界を行き来しながら、キャッチーなメロディと実験的な音響レイヤーが見事に均衡した、ジャンルの枠を超えた独自の美学を確立した一枚!

2025年リプレス!遂に満を持して登場。あの『Green』を凌ぐ人気を誇る、長年失われていた吉村弘最高峰のアンビエント・クラシックこと1986年作品『Surround』が〈Light in the Attic〉配給の〈Temporal Drift〉レーベルより待望の公式アナログ再発!日本の環境音楽のパイオニアであり、都市/公共空間のサウンドデザインからサウンドアート、パフォーマンスに至るまで、傑出した仕事を世に残した偉才、吉村弘。その最難関の音盤として君臨してきた幻の一枚が、今回史上初の公式アナログ・リイシュー。ミサワホームから依頼されて録音された作品で、これらは同社の新築居住空間をより充実させるために設計された「アメニティ」として機能することを目的としていた環境音楽作品。吉村自身による当時のライナーノーツに加え、オリジナル・プロデューサーであった塩川博義氏による新規ライナーノーツも同封(日/英)。 MASTERPIECE!!!!!!!!!!!!!!!!!

ロサンゼルスのビートメイカーとして、〈Stones Throw〉〈Brainfeeder〉〈All City〉〈Hyperdub〉など数々の重要レーベルから作品を発表してきた Samiyamが、自身のもう一つの情熱であるデスメタルに捧げた異色の作品。SAMIYAMは過去5年間でデスメタルとホラー映画に傾倒しており、古典的なバンドを掘り下げる中で生まれたアイデアを、ドラムプログラミングやサンプリングに取り込み、メタル的な重厚感をヒップホップの感覚で再構築。収録された13のビートは、ラフで荒々しくも緻密に仕上げられ、彼の持ち味である硬質なグルーヴと異形のギター的質感に加工されたサンプルやノイズが融合することで、これまでにないダークでユニークな音世界を生み出している。ヒップホップ・ビートとメタルの質感が激しく交錯する実験的なアルバムでありながら、単なる実験にとどまらない深みを備えており、サンプルを歪ませ、反転させ、ノイズと絡めながら構築されたトラック群は、従来のSamiyam のイメージを裏切りつつも、その根底にある ビートへの執着 をより強調するものとなっている。そのサウンドは、デスメタルの攻撃性とホラー映画的な不穏さを抱えつつ、あくまでビート・アルバムとしての機能性を失わず、ヘヴィなリフの残響や、ノイジーな音響処理が織り込まれた中で、独特のグルーヴが絶えず脈打ち、新しい形のビート・アートを提示している。寡作ながら常に注目を集める彼のキャリアの中でも特に挑戦的で刺激的な一枚。