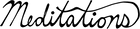MUSIC
6089 products




アヴァンギャルド・ジャズとフューチャー・ソウルで知られるコルネット奏者、Ben LaMar Gayの事実上のデビュー・アルバムである2018年作『Downtown Castles Can Never Block The Sun』が〈International Anthem〉創立11周年記念リイシュー・シリーズとして、新しい帯と、ミュージシャンであり長年のBen LaMar Gayの友人、コラボレーターであるGira Dahneeによる写真と新しいライナーノーツが掲載された4ページのインサート・ブックレットが新装されてめでたくもリイシューされました!本作は、この伝説的なシカゴの作曲家/即興演奏家/ルネッサンス・マンを世界に紹介するための試みとして、彼が7年かけて制作した(ものの、まだ実際にリリースする努力はしていなかった)7枚のアルバムからの楽曲をコンパイルしたもので、スティーブ・ライヒ風のサウンドスケープから、ドン・チェリー風のポリリズム、ベン・ホルヘ風のヴォーカルと弦楽器の調べまで、ジャンルを飛び越えるゲイの才能が発揮されている。


エチオ・ジャズの創始者、ムラトゥ・アスタトゥケが約10年ぶりに発表したスタジオ・アルバム『Mulatu Plays Mulatu』が〈Strut Records〉より登場。60〜70年代にエチオピア音楽の歴史を塗り替えた自身の代表曲を、熟練のUKバンドやアディス・アベバのジャズ・ヴィレッジに集う現地ミュージシャンと共に新たなアレンジで再演した一枚。西洋ジャズの洗練されたアンサンブルに、エチオピア伝統楽器クラール、マセンコ、ワシント、ケベロ、ベゲナの響きを重ね、豊かな質感と複雑なリズム、自由な即興で名曲たちをアップデート。ムラトゥが長年追い求めてきた「エチオ・ジャズを世界に伝える」という夢の集大成であり、近代的な音楽理論やジャズ教育を受けたわけではないけれど、古くから口承や地域の慣習の中で培われてきた伝統的なエチオピア音楽の中で独自に音楽理論や演奏法、作曲技法を基礎付けた、「エチオピアの無名の音楽科学者たち」への敬意も込めた作品。ロサンゼルスのカルロス・ニーニョ、キブロム・ビルハネら現代アーティストも参加し、伝統と現代性、エチオピアと西洋が深い次元で融合されている。巨匠!


ボーカルのZack Borzoneとプロデューサー/ドラマーのSam Pickardを中心にフィラデルフィアで結成され、のちにニューヨークに移ってからJack TobiasとSaguiv Rosenstockが加入した4人組バンドYHWH Nailgunのデビューアルバム『45 Pounds』がロンドンの大名門〈AD 93〉から登場。ポストパンク、ノイズロック、実験音楽を融合させたサウンドが特徴的で、バンド名はヘブライ語の「ヤハウェ」を意味するが、その音楽性はむしろ俗世的で、混沌とした暴力的なサウンドにこそ本質がある。宗教的というよりも、人間的な激情や混乱を表すために、聖書的なイメージや象徴を借用している。Pitchforkが「このデビュー作は、わずか21分で実験音楽とアヴァンギャルドの世界を再構築する」と評したように、圧倒的なテンションで、ギターは軋み、ドラムは暴れ回り、すべての音が過剰で、歪んでいて、それでいて妙に中毒性がある。ロックというフォーマットに内在する衝動や混乱を最大限に引き出した、ある種の"破壊と再構築"の儀式とも言えるとんでもない一枚!

シカゴで最も重要かつ革新的なハウス・ミュージック・レーベルのひとつである〈Dance Mania〉、その決定的な回顧録として高い人気を誇っている2014年にリリースされた〈Strut〉による超名作コンピレーション『Hardcore Traxx: Dance Mania Records 1986-1997』がこのたびめでたく再プレスされました!!80年代半ば、〈Trax〉や〈DJ International〉といった老舗レーベルに代わる生々しいレーベルとして誕生した〈Dance Mania〉は、90年代に入ってもシカゴのストリート・クラブ・ミュージックを代表し続け、ゲットー・ハウス・サウンドのパイオニアとなった。本作は1986-1997とレーベルの全盛期からのストーリーをたどるもので、マーシャル・ジェファーソンの卓越した「7 Ways」のようなクラシックから、ヴィンセント・フロイド、ティム・ハーパーのディープなカット、DJディオン、ポール・ジョンソン、DJファンクのゲットー・ハウス・フロアバーナーまで、〈Strut〉によるこのレーベルへの究極のトリビュートとして、クラシック、ゲットー・ハウスのアンセム、隠れた名曲を綿密にキュレーションしたコンピレーションとなっている。〈Dance Mania〉の協力を得て制作され、ダフト・パンクにインスパイアされた人気のティーチャーズ・ミックスのクリエイターであるコナー・キーリングが、ランサムノートのマイルズ・シンプソンと共にコンパイルしている。レーベルの包括的な歴史、DJクリッシー・マーダーボットによるアーティスト・インタビュー、貴重なアーカイブ写真も付属。


デンマークはコペンハーゲンを拠点に活動するジャズ・ベーシストJonathan Bremerと、ピアニストのMorten McCoyによるデュオ、Bremer/McCoyによる〈LUAKA BOP>からの2019年作『Utopia』が入荷できました。冷たい風の吹く冬のコペンハーゲンで2週間かけて行われたセッションを、一切コンピューターは用いず、全てテープを使用して完全アナログで製作された本作は、一音一音、丁寧に紡がれる美しいメロディにスムースなグルーヴと、以後続いていく名作『Natten』『Kosmos』の世界を予感させる音像。ほとんどの曲が実は歌詞があったものをインストゥルメンタルとして再構築したという収録曲たちはどれもさながら無言歌のよう。ウーリッツァー、ピアノのきらめくような音とタンゴのような雰囲気を持つ暖かくゆったりとしたベースラインが好バランスな「Højder 」やヴァイオリンとダビングされた鍵盤が幽玄なグルーヴを醸し出す「Tusmørke 」など、ジャズファンからアンビエントファンまでお勧めできる好内容!


クラシックの世界的大名門〈Deutsche Grammophon〉にも在籍するポーランド出身のピアニストHania Raniによる2020年のアルバム『Home』を、英国の現代ジャズの大聖地的レーベル〈Gondwana Records〉からストック。ピアノ中心の作品だったデビュー・アルバム『Esja』から楽器やサウンドの方法論をより拡張した内容となっており、エレクトロニクスやヴォーカル、ベース、ドラムなどを加えながらワイドスクリーンなサウンドを追求したモダン・クラシカル/ピアノ・アンビエントの傑作盤!

Peak OilやKrankyで知られるBrian Footeが始動した新レーベル〈False Aralia〉の第3弾リリースとして、Externalism名義による謎めいた新作が登場。Zero Key、Selfsameに続くかたちで届けられる本作は、艶やかなダブ・ソウルと荒削りな実験的な音響処理を行き来する、4トラック構成のEPで、オープニングは、Sadeを思わせる夢見心地なヴォーカルの断片と、Rhythm & Sound直系のベースラインが交差する、ホログラフィックなダブ・ソウルの逸品。その後のトラックでは、徐々にその構成が溶けはじめ、声はエコーとノイズの中に消え、ビートはザラついた質感へと変容してゆく。最終曲では、水中で光がきらめくような揺らぎと、アンビエント的な音響の濃度が高まっていく。プロジェクトExternalismの正体は不明だが、Topdown Dialecticの変名、あるいは集団名義の可能性もと推測されている。この正体不明な感覚自体がこのシリーズの魅力とも言えそう。


眠れない深夜、揺れる内面に寄り添うような、微細で緻密な音楽!Peak OilやKrankyで知られるBrian Footeが始動した新レーベル〈False Aralia〉の第1弾リリースとして、Izaak Schlossman(aka Zero Key)によるアルバム『False 01』が登場。Schlossmanはこれまで/Aught、S Transporter、Loveshadowといった名義で静かに活動し、そのミニマルかつ深淵なサウンドで一部のリスナーから熱狂的な支持を得てきた。Jan Jelinek、Actress、Purelink、Huerco S.周辺の音に共鳴する、アンビエント・ダブとリズミックな実験の間を漂う本作は、透明感のあるヴォイス断片や、霞んだステッパーズ・ダブ的構造、そしてミニマルでスリムなグルーヴが、まるで夢のなかのフロアを彷徨うように展開。うっすら酩酊しながらもダンサー目線を失わないビート感覚、情感を帯びたメルト感と、深夜のブルーズ感覚が交錯する、心の奥に静かに染み込む一枚。


NYアンダーグラウンドのキーパーソン、Alien DことDaniel Creahanが、〈Theory Therapy〉から初リリースとなる最新作『For the Early Hours of a World in Bloom』を発表。前作『Spiritual World』はアンビエント寄りだったが、本作ではフロア仕様のダブ・グルーヴが軸になっており、繰り返しと微細な変化によって、持続的なうねりを生み出している。中でも13分に及ぶ「Breather」は、Ben Seretanのギターを迎えた静かなハイライトになっており、じんわりとした低音と変化し続けるトーンが絡み合い、静かにトランス状態へ導かれる。パンデミック直後の静けさの中で制作されたという背景もあり、全体には希望と内省が共存したような、やわらかな浮遊感がある。深夜から早朝にかけての、あの魔法のような時間帯を封じ込めたような一枚。


大人気ユニット、Salamandaの片翼!韓国・ソウルを拠点に活動するプロデューサー/DJ、Yetsubyによる最新アルバム『4EVA』が、UK新興レーベル〈Pink Oyster〉の第1弾として登場。ブレイクビーツ、フットワーク、ジャングル、IDM、アンビエント、クラブ・ミュージックを自在に横断しながら、デジタル/アナログ/アコースティックの音響を緻密に編み上げた全10曲。遊び心溢れるサウンド・デザインと、内省的かつ親密なムードが共存する、Yetsubyのソロ作品として極めて完成度の高い一枚です。限定300部。




フランスはリヨン拠点、〈Second End Records〉主宰のJonnnahが、グラスゴーの優良レーベル〈co:clear〉から、揺らめくアンビエントと歪んだトリップホップ、ねっとりした低音が溶け合う没入型の電子音楽『Me, With You』をリリース。全7曲は、クラブの大型システムでも、ヘッドフォンでの内省的なリスニングでも成立する二面性を持って構築されており、フロアと個人空間のどちらにもフィットする作りになっている。オープニングにはButtechnoことPavel Milyakovが参加し、アンビエント・シューゲイザーなギターのレイヤーが霧のように立ち上がり深い没入感をもたらし、Jonnnahは、繊細なビートとメロディで、浮遊感と感情に満ちたスイートな流れを描く。トリップホップからハイパーポップ、D&Bまでを内包しつつ、耳元でささやくような電子音の私小説。クラブミュージックの境界線を優しくぼかすような、静と動、広がりと親密さが交錯する、現代アンビエント/エレクトロニカの秀作。


リプレス!豪州前衛音楽の一大聖地〈Black Truffle〉主宰者としてもその卓越したキュレーションを披露してきたマルチ奏者Oren Ambarchiが、実験的サックス奏者Mats Gustafssonらも参加するアヴァン・ジャズ・トリオこと”Fire!”と組んだ、2022年に〈Drag City〉より発表されていた『Ghosted』。ファンク・ジャズから、パーカッシヴでポリリズミックな骨格、牧歌的なアンビエント、ポスト・クラウト・ドローン、煌めくサウンドトラックの夢想までもが連なっていく、新たな地平へのフュージョンと言える、全くユニークな一作!


豪州前衛音楽の一大聖地〈Black Truffle〉主宰者としてもその卓越したキュレーションを披露してきたマルチ奏者Oren Ambarchiが、実験的サックス奏者Mats Gustafssonらも参加するアヴァン・ジャズ・トリオこと”Fire!”と組んだ最新アルバム『Ghosted II』が〈Drag City〉から登場。ファンク・ジャズから、パーカッシヴでポリリズミックな骨格、牧歌的なアンビエント、ポスト・クラウト・ドローン、煌めくサウンドトラックの夢想までもが連なっていく、新たな地平へのフュージョンと言える、全くユニークな一作!


Oren Ambarchi、Johan Berthling、Andreas Werliinによるトリオ作『Ghosted III』が〈Drag City〉より登場!ジャズやクラウトロックの感覚を土台にしつつ、今回はより自由でゆるやかな空気をまとった一作で、前2作に比べて、アメリカーナやドリームポップ、ブルースといった新たな要素もにじみ出ていて、細部のニュアンスにフォーカスしたサウンドが特徴的。冒頭曲では、チリチリとしたギター、よれたリズム、ほどけたベースが絡み合い、フィリップ・グラス風の浮遊感が心地よい。曲ごとにテンションを緩めたり高めたりしながら、美しいドリームポップ風ポストロックへと昇華。全体として、即興的な緊張感は保ちつつも、より開放的で感覚的な作風で、シリーズ中でも特にメロディアスで親しみやすい内容になっている。


David GrubbsとJim O’Rourkeによるユニット、Gastr del Solの代表作であり、ポストロック/実験音楽の重要作として知られている1996年のアルバム『Upgrade & Afterlife』がめでたくリイシュー!フォーク・ミニマリズム、アヴァンギャルド、電子音響が混ざり合い、常に予想を裏切る構成が特徴的。冒頭の「Our Exquisite Replica of ‘Eternity’」では、映画音楽のサンプルやドローンを用いて、異様で感情的な風景を描き出し、アルバム全体の方向性を示す。続く曲では、弾き語りが抽象音響へ変化したり、歪んだリズムや断片的なボーカル処理などが登場し、聴くたびに新たな発見がある作りになっている。ラストはJohn Faheyの「Dry Bones in the Valley」のカバーで締めくくられ、ゲストのTony Conradのヴァイオリンが、アメリカン・フォークと前衛音楽の橋渡しをするように響く。批評家からも「フォークとアヴァンギャルドが互いを抽象化しながら融合している」と高く評価され、ジャケットに使われたRoman Signerの作品《Wasserstiefel》も含め、コンセプチュアルで不思議な魅力を放っている。実験音楽ファンにとっては聴き逃せない名作!


Sir Richard Bishop(Sun City Girls)によるひとりアコースティック・ギターだけで挑む、原始衝動むき出しの一枚はアメリカン・プリミティヴを踏まえつつも、そこにインド古典音楽のラーガの解釈を織り込み、秩序や安定から外れたリズムと動きに焦点を当てた、荒々しい独奏集。彼が語るところによれば、目指したのは基本への回帰で、エフェクトも電気もオーバーダブも一切なし、あるのはギター一本と自分の手だけ。アメリカン・プリミティヴが「原始」と名乗りながら、実際には整然としすぎていることへの反発から、あえて無鉄砲に、予測不能な展開を打ち出す。その姿勢は、山奥で誰からも教わらず独自のフォークロアを鳴らす孤高のヒルビリーをイメージしたものだという。『Salvador Kali』『Improvika』『The Freak of Araby』といった探求的な作品群で培ってきた感覚を、ここでは極限まで削ぎ落としており、9曲それぞれが、深い森をひとり分け入るかのような探索であり、外界と切り離された音楽の放浪記でもある。ヒルビリーの神秘家による異形のフォーク伝承。

Red Krayolaを率いたテキサス・サイケ・シーンの重鎮であり、70年代後半以降は、The RaincoatsやThe Monochrome Set、The Fall、Pere Ubuに至るまで、〈Rough Trade〉周辺のバンド作品にも顔を出して回ったレジェンド、Mayo Thompson。1969年に短命なレーベル〈Texas Revolution〉からリリースした鬼レアなアルバム『Corky's Debt To His Father』が〈Drag City〉よりリイシュー。若さ、セクシュアリティ、人間の坩堝を全くユニークな方法で表現した、その最高傑作の一つとしてキャリア全体を通して輝き続ける屈折的アート・ロック・アルバム!ボーナストラック入りの7インチ・シングル盤も付属。


ブラジル・サンパウロ郊外ディアデマから登場したDJ Kによる、ファヴェーラのリアルを突きつける最新作『Rádio Libertadora』が〈Nyege Nyege Tapes〉より登場。17歳からFL Studioで制作を始め、わずか数年でブラジリアン・ファンキの枠組みを塗り替えたDJ K。独自に生み出したBruxaria(魔術)と呼ばれるスタイルは、暗く、ノイジーで、サイケデリック。前作『Pânico no Submundo』でその片鱗を見せたが、本作ではさらに過激で、政治的な鋭さを増している。アルバム冒頭、1969年の軍事独裁時代に共産ゲリラ指導者カルロス・マリゲーラが地下ラジオで放送した反体制スピーチをサンプリングし、「軍事独裁に死を!」と高らかに宣言。MC Renatinho Falcãoを迎えたそのトラックでは、金属質なノイズ、爆音ベース、歪んだディストーションが入り乱れ、ファヴェーラを「見えない戦争」の戦場として描き出す。90年代ブラジルのプロテスト・ラップに通じる闘争のスピリットと、腐食した電子音の荒野。『Rádio Libertadora』は単なるアルバムではなく、サンパウロの地下から鳴らされるマニフェストとも言うべき一枚。


ドキュメンタリー制作や展覧会キュレーションなど幅広い表現活動で知られるViolence Gratuiteによる初めての音楽作品『Baleine à Boss』が入荷できました!ウガンダの首都カンパラを拠点とする、東アフリカの伝統的な音楽と現代の電子音楽を融合させた現行のアンダーグラウンドで革新的なサウンドを世界に紹介するレーベル〈nyege nyege tapes〉のサブ・レーベルである〈Hakuna Kulala〉からのリリースで、本作もフレンチ・ポップ、ラップ、ノーウェーブ、エレクトロニクスの混淆とも言える独自の世界!パリ郊外育ちで、ブルターニュとカメルーンにルーツを持つ彼女は、文化的バックグラウンドを反映させながらも、フレンチ・ポップ的なメロディー、トラップやグライムから影響を受けたビート、そして幽玄なヴォーカルを自在に行き来しながら展開。トリッキーやリジー・メルシエ=デクルーらに通じるダークで不穏な空気を漂わせつつ、ダンスホールやカリブ音楽のリズムも取り込むなど、常に予測不能な流れを作り出している。ポップとアヴァンギャルドの狭間で揺れ動く、自由奔放で多層的な作品!!


ウガンダの首都カンパラを拠点とする、世界各地のオルタナティブなエレクトロニック・ミュージックやエクスペリメンタル系を自由に追求するレーベル〈Heat Crimes〉による、ハンガリー系トランシルヴァニア出身Réka Csiszérの2作目のソロアルバム『Danse des Larmes』。本作は、子ども時代の孤独や無意識のトラウマをテーマに、東欧の民謡、インダストリアル、ダークアンビエント、古いホラー映画音楽を溶かし合わせた、身体と精神の境界があいまいになるような、幽玄で冷たいサウンドスケープ。デビュー作『Veils』に続き、演劇や映画、オペラへの関心を滲ませつつ、今回はより個人的な記憶と未来的なビジョンを交錯させている。冒頭の「Eden X」では、うめくシンセと聖歌のような声が溶け合い、不穏な世界に誘我、続く表題曲では、歪んだフォークの要素が顔を出し、夢と現実の境界を揺さぶる。ハンガリーの巨匠Mihály Vígへのオマージュも含まれ、彼の曲をエーテルのようなドリームポップに再構築している。全編を通して、トラウマや過去の記憶が幻想的に変質していくような、暗く湿っていながらも不思議な美しさに満ちたアルバムとなっている。

中東地域のネットカルチャーとグローバル・ベース/クラブ・ミュージックの接点を捉え続けてきた〈HEAT CRIMES〉から、注目のコンピレーション『REEL TALK - BEST OF DOUYIN TRACKS』が登場。中国のショート動画プラットフォーム「抖音(Douyin)」上で流通したサンプリング音源やクラブトラックをキュレートし、カットアップ、スクリュー、トランス、スピードコア、トラップ、アンビエントまでを雑多に飲み込む全20曲。ネット特有の速度感と無作為さ、そして奇妙なエモーションが交錯する、デジタル以降のサウンド・アーカイブとしての一枚。カルト的人気を誇るシリーズ最新章。

2021年東京、ハリクヤマクの曲だけでDJをするという珍しい機会があった。普段だとエフェクターやミキサーなど、まぁまぁの量の機材を運んでライブ・ダブミックスをしているんだが、DJセットときた。
しかし、リリースの有無に関わらず、自分の中で一度完成した曲だけをプレイするのはDJをやってて、自分が面白くないなと思った。そこで、フライトまでの2日間、色々な曲のダブミックスを録音し、それをCD-Rに焼いて持っていったのである。沖縄に帰ってしばらくして、そのCD-Rを聴き返したら、色々と荒いなと感じながらも、それ含め良い!と思い、配信することにした。それが『島DUBPLATE for Tokyo 2021』である。
それからまた月日は経ち、2024年。なんとこれをレコードにしてくれるという話がきた。最高だ!最高だけど、レコードにするには、惜しい曲や物足りなさがある。配信とレコードとでは訳が違う。一発録りの2ミックスだから、重ねるしか無いと思った。CD-Rから曲を選び、
A2 "Ayahaberu"には盟友MAKI TAFARIによるフルートソロをオーバーダブ。
A4 "Turubaimun"にはAKANMIMANにトースティングしてもらった。彼にとっては初めての録音だった。
B1" Kuduchi Behshiはスプリングリバーブを叩いたノイズやシンセをオーバーダブ。
また、レコード化のために新しくダブミックスも録音した。
A3 "Pacific Dub"は個人的には沖縄レゲエ史上最高の曲、石垣吉道の"Key Stone"をリディムを作りかえダブミックス。
B4 "Dub Season"はこちらも盟友、稲嶺幸乃との共作である”四季口説"をダブミックスしている。
Text by HARIKUYAMAKU