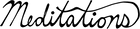MUSIC
6071 products

uon / shy / Caveman LSDなど多様な活動でも知られるSpecial Guest DJがここ10年かけて築いてきた、実験的エレクトロニックの地下迷宮。その集大成のような一枚『Our Fantasy Complex』が自身のレーベル〈3XL〉から登場。Special Guest DJはベルリンを拠点にダブ・アンビエントや滲んだクラブ・テクスチャ、ローファイな夢想空間を行き来してきたが、本作は、その入り組んだ美学を凝縮したもので、怒り、官能、夢といった感情のもやを音に転写したような内容。シューゲイズやダブテクノ、D&Bのエッセンスが断片的に浮かびつつも、ジャンルには還元されないまま、呪術的な音響の絡まりとなっている。、Ben Bondy、mu tate、Arad Acidといった盟友たちの手も加わり、奥行きを増したサウンドは、内省とクラブの残骸を曖昧に溶かすような、よりダークで汚れたサイケデリア。

Lucy DuncombeとFeronia Wennborgによる、人工音声ツールを駆使して4年かけて作られた、ヴァーチャル合唱シンフォニーとも言うべき作品『Joy, Oh I Missed You』が〈Warm Winters Ltd.〉より登場。詩的なサウンドと、機械の故障じみた奇妙さが入り混じった音像は、音声合成やAIボイス解析などの技術を使い倒し、あえて人間の声を完全に模倣せず、失敗やひずみに耳を澄ますアプローチで、。フランソワ・デュフレーヌやオノ・ヨーコ、Phewらの声の実験を、現代のツールでアップデートしたような内容とも言える。Duncombeの奇怪な電子声と、Wennborgの硬質なサウンド処理が絶妙に絡み合い、どこからが人間の声でどこからがデジタルの模倣か判別がつかない。時には機械の故障のように、時には祈りのように、ピッチがずれ、破裂し、ため息のような断片が折り重なって、異形のコーラスが立ち上がる。タイトルどおり、喜びと喪失の間で揺れるような感情の振幅をもった作品で、コンセプトは実験的だが、音楽としての美しさや感情的な深みもしっかりとしており、聴き応えある充実作。

現代アンビエントの最重要人物のひとり、Perilaがアルバム『omnis festinatio ex parte diaboli』で、ついに〈West Mineral〉から初登場。これまでの夢幻的なサウンドスケープから一歩踏み出し、Dilloway的なテープノイズ、ASMRのような親密な質感、フリッツしたダブテクノ、レイヤーされた声のドローン、儀式的なマントラといった要素が絡み合う、濃密で異形な音世界を表出している。音楽はより深く潜り込み、Perila自身が語るトランス状態をそのまま聴覚体験として再現するかのよう。マントラのように繰り返される「thunder me」、そして全編ヴォーカルによる「hold my leg」などは、滲んだ密室的親密さと崇高さを漂わせている。古代的な感性と、テクノグノーシス的な感性が共存するサウンドでありながら、あえて余白に奇妙さを残すバランス感覚が絶妙で、催眠と官能が交錯する、現在の実験音楽の最前線ともいうべき内容!

ロンドンとマンチェスターのスタジオで長年かけて作られたダークで幻覚的な音世界を描いたDemdike StareとCherrystonesによるコラボ作『Who Owns The Dark?』。ジャンルを飛び越えるその音像は、ノーウェーブ、プロト・テクノ、インダストリアル・コンクレート、サイケの残骸を混濁させたもので、Cherrystonesの過去作『Peregrinations in SHQ』の世界観を引き継ぎつつ、Demdike Stareらしいねじれたサウンドスケープと、レコードディガーならではの特異な音素材が交錯。ぼろぼろのテープ編集や、粗野で即興的なリズム、ヒップホップ的サンプルの断片、幽霊のような声が渦巻く。次々と音の地形が変化していく構成で聴き手は不穏な夢の中をさまようような感覚に陥るが、要所に差し込まれるLaura Lippieのボーカルが、狂気寸前の世界にかろうじて人間味を残しており、混沌の中のかすかな灯となっている。ECM的静謐さ、Earthの重量感、Dilloway的ローファイ・アヴァンギャルドを結びつけるような、まさに音による降霊術。


グラス・ビームスやクルアンビン好き必聴!!今回新たに〈Ninja Tune〉傘下のレーベル〈Technicolour〉との契約が発表されたユーフは、ロンドンを拠点とする4人編成のインストバンドであり、近年、東洋と西洋を掛け合わせた摩訶不思議な音楽で人気を博すグラス・ビームスを輩出した〈Ninja Tune〉の今の方向性の一つを示すように、世界各地の音楽からの影響を融合した唯一無二のサウンドで熱い注目を集めている。
5曲で構成される『Alma’s Cove』は、日常のストレスから解放され、自然や物事とのつながり、そして共鳴の感覚を通じて、リスナーを瞑想的な音の旅へと誘うサウンドスケープである。バンドは「『Alma’s Cove』は、ストレスのない夢のようなトロピカルな空間で、心が満たされ、今この瞬間を感じられる場所。自分のペースで楽しめる静かな楽園だ」とコメントしている。「このEPを制作するうえでの主な目的は、私たちのロンドンでの生活−−ストレス、不安、圧倒される日々−−とは真逆の空間を作り出すことだった。自然とのつながりを取り戻し、“今”を楽しむための夢の国なんだ」。
オーガニックな質感、きらめくような音のディテール、サイケデリックなリズムが豊かに織り込まれたタイトルトラックはリスナーを『Alma’s Cove』の穏やかな世界へと誘う。自然の中を歩きながら、その音や景色を感じ取り、その美しさに身を委ねているような体験がそこにはある。
ユーフ|Yuuf
世界各地の音楽的影響を融合するという音楽理念のもとで活動するユーフ。メンバーそれぞれの出身地も、スイス、デンマーク、フランス、イギリスと異なる。そのサウンドはクラシックなスペインギター、アメリカーナのサウンドスケープ、そしてスタジオジブリのサウンドトラックからもインスピレーションを受けている。2024年の夏にデビューEP『In The Sun』をリリースし、Spotifyだけで150万回以上のストリーミング再生を記録。BBC 6Music、KEXP、KRCWなどのメディアからも注目を集めている。EPと同時に公開された『The Sun』のライブ・セッション映像は、YouTubeで180万回再生を超えるヒットとなっている。


今UKで最も注目を集める奇才プロデューサーVegynと、スポークンワード・アーティストFrancis Hornsby Clarkの新プロジェクトHeadacheによるアルバムがリプレス!
Frank Oceanをはじめ、Travis ScottやJames Blakeなど著名アーティストとのコラボレーションでその名を知らしめるVegynと、スポークンワードのアーティストFrancis Hornsby Clarkによる最新プロジェクトHeadacheのアルバム『The Head Hurts but the Heart Knows the Truth』が、Vegynが主宰する〈PLZ Make It Ruins〉から発売!
Headacheは、Vegynがプロデューサーを務め、Francis Hornsby Clarkが作詞を手がけ、それをAIが演奏するというシュールで新しいプロジェクト。
Vegynが紡ぎ出す爽やかで心休まるインディーポップに、Francis Hornsby Clarkが作詞したリリックを、AIがまるで狂人の戯言のように、愛や失恋、絶望などについて延々と語っている。その体験から得られるエフェクトは決して「Headache(頭痛)」ではなく、聴く者は、むしろカタルシスを感じ、頭もスッキリするであろう、アブストラクトで未来的、サイケデリックかつユーモラスな全16曲を収録。

キャリア屈指の人気を誇る名曲「Girl/Boy Song」を収録したエイフェックス・ツインの代名詞的作品。
自らの本名を冠し、同名の亡き兄へと捧げられた作品(1996年リリース)。アナログ・シンセからソフトウェア・シンセへと制作機材もシフトし、痙攣するビートにクラシックやトイ・ミュージックを掛け合わせ、無二のポップ・ミュージックへと昇華された90年代を代表するアルバム。ドラマチックにたゆたう弦楽器とエモーショナルにのた打ち回るビートとのコントラストが琴線を直撃する名曲「Girl/Boy Song」は本作に収録。







2025年リプレス!「アルヴィン・ルシエ meets マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン」と評される名作!Jim O’Rourkeの盟友でもあるポルトガル実験音響界のレジェンドであり、当店でも大人気のレジェンドRafael Toral。同氏が95年にセカンド・アルバムとして残した傑作『Wave Field』がリマスタリング仕様で〈Drag City〉よりアナログ再発。Toralが「音符ではなく音そのもの」に焦点を当てる転換点となった作品。Alvin Lucierの『I Am Sitting in a Room』や、1993年にリスボンで鑑賞したNirvanaとBuzzcocksのライブ体験(特に、会場の劣悪な音響が生み出した「液状化したロックサウンド」)からインスパイアされたとの事。その他、My Bloody Valentineの『Loveless』やSonic Youthなどからの影響を受けつつも、それらを独自に昇華した本作は、90年代のポルトガルにおける特異な実験的音楽シーンを代表するドローン/アンビエントの傑作。名エンジニア=Rashad Beckerによってマスタリングされ、オリジナルの意図をより忠実に再現した決定版。ロックやアンビエント、ドローン、ノイズの境界を曖昧にする、時代を超えたマスターピースです!


2025年リプレス!Rashad Beckerによるマスタリングにて30周年記念エディションとしてヴァイナル再発!ボーナストラック付属。Brian EnoやRobert Frippからインスパイアされた音響ドローン・ギター・サウンド!90年代には「最も才能豊かで革新的なギタリストの一人」と称され、そして、Sonic Youthのメンバーたちにも愛されたポルトガルの一大音響作家、Rafael Toralが同国のAnAnAnAより1994年にリリースし、ジム・オルーク氏の名音響レーベル、Moikaiからも再発されているファースト・アルバム名作。
長らく廃盤であったトラル初期の重要作品が嬉しい再発!イーノのアンビエント作品を爪弾くJohn Faheyのごとく、美麗で優しい極上アンビエント・ドローン。彼が実際に影響を受けている通り、My Bloody Valentineを感じる人もいるでしょう。ゆっくりと動くノスタルジックな音色は懐かしいフィルム写真の情景を心に浮かばせるかのようであります。たとえ雑多な街角にいても、自然の中へと還るような、そんな穏やかで優しい気持ちになる響きです。私たち生きとし生けるものの原風景というと大げさかもしれませんが、私はそのようにすら感じます。まさにタイムレスな一枚。


La Monte YoungやPauline Oliveros、Alvin Lucierのもとで学んだアメリカのヴィジュアル・アーティストにしてミニマル作家Arnold Dreyblatt。Yoshi Wadaの名盤もリリースしていたIndia Navigation Recordsから1982年にリリースされていた、ミニマル・ミュージック傑作。バス・ビオール(中世の弦楽器)、小型アップライトピアノ、ポータブルパイプオルガン、ハーディガーディにより、強度、速度、音色を変化させた恍惚なパターンを様々に収録。


Thinking Fellers Union Local 282のアブストラクトで荒々しく、実験性の強い一面が浮かび上がる『The Funeral Pudding』が〈BULBOUS MONOCLE〉よりリイシュー。本作ではベースのAnne EickelbergとギターのHugh Swartsが多くの曲でヴォーカルを担当している点がユニークで、Davies/Hagemanのツインフロントがメインだった他の作品とは一線を画す構成で、「Waited Too Long」や「Heavy Head」ではEickelbergの高らかな歌声がバンドの新たな魅力を引き出している。スリリングな展開と構成が光る「23 Kings Crossing」では、彼らならではの音響世界が表現されており、ノイズ、サイケ、ポストパンク、ポップ、アヴァンギャルドが混然一体となった独特の音楽性となっている。緻密な音作りとソングライティングの完成度が際立つ、バンドの捉えどころのなさと筋の通った狂気が詰まった一枚。


1970年代初頭、ポートランドのブラック・コミュニティが育んだジャズ、ファンク・バンドThe Gangstersによる40年以上も未発表のまま眠っていた幻の音源集。The Gangstersには、後にグラミー受賞やB.B.Kingのバンドへの参加など、それぞれが華やかなキャリアを歩むことになる若き才能たちが在籍しており、中心人物はトランぺッターで後に名教育者ともなるThara Memory。本作は彼の指揮のもと、Ripcord Studiosで1970~72年に録音されたセッション音源を収めたもの。タイトなグルーヴと、洗練されたアレンジのもと、若き才能たちが初めて交差し、炸裂した一瞬の閃光のようなアルバムで、その一体感とスリルは、今聴いても鮮烈。また、バンドメンバーによるオーラル・ヒストリーや未公開写真、現地文化団体の支援による豪華パッケージが付属しており、単なる再発にとどまらず、失われた地域文化と音楽遺産を掘り起こす重要な記録でもある作品。

マリの伝説的ギタリスト、アリ・ファルカ・トゥーレによる5thアルバム『Ali Toure Dit "Farka"』が、〈Sonafric〉により公式リイシューされたもの。長いあいだ再発されてこなかった初期音源群のうちの1枚で、当時の空気をそのまま閉じ込めたようなオリジナル・ジャケットとラベルを忠実に再現。リマスタリングも丁寧に施され、当時の録音が鮮やかに蘇る。本作では、アリ・ファルカ・トゥーレの音楽がより洗練され、ブルースの語法と西アフリカの伝統音楽とのハイブリッドが明瞭に感じられる。ギター・プレイは流麗かつ反復的で、デルタ・ブルースを通過したアフリカン・リズムとしての独自性が際立っており、声はより表情豊かになり、物語を語るようなグリオ的な語り口が深みを増している。この頃のアリは、まだ世界的には無名に近かったが、地元マリではすでに高く評価されており、その特別な時期の、土着性と普遍性のはざまにある強烈な個性を感じられる名盤。


Matthew Youngの新作『Undercurrents』が〈Drag City〉より登場!ニューエイジ、実験音楽、アウトサイダー・ポップの狭間を旅する夢のようなサウンドスケープで、ハンマーダルシマー、電子マリンバ、ハープ、ピアノを中心に、きらびやかで少しずれた感触の音が全編に漂い、どこか夢遊状態のような聴覚体験へと導かれる。ミヒャエル・オシェア、ダニエル・シュミット、ムーンドッグあたりを思わせる音世界は、リズムと旋律がゆらゆらと交差するリズメロディックな構造のなかで展開される。なかでも12分に及ぶタイトル曲「Undercurrents」は、ジャズ的なブルースフィールとアヴァン・クラシカルな展開が織りなす異次元のサウンドコラージュで、徐々にドローンがにじみ出す後半には、まるで別タブが開いてしまったかのような奇妙な感覚すらある。幅広い音楽性を内包しながら、奇妙にもしっくりとまとまっており、実験と親しみやすさ、冷たさと温かさが共存する、まさにMatthew Youngの世界。


「彼女はビリー・ホリデイのような声で、ジミー・リードのようにギターを弾くんだ」(Bob Dylan)。今は確信を持って言える、60年代最高の女性シンガーの1人。1960年代前半からNYグリニッチ・ヴィレッジで活動、ステージでも共演していたボブ・ディランからも後にフェイバリットに挙げられるなどしていたものの、決して商業的成功をおさめることのなかった孤高の女性シンガー、Karen Dalton。1969年の〈Capitol〉デビュー作『It's So Hard To Tell Who's Going To Love You The Best』がシアトルの〈Light In The Attic〉よりアナログ・リイシュー!本作では、Lead Belly、Fred Neil、Tim Hardinらの名曲をカバーし、アメリカのクラシカルなソングライティングの世代を横断。ダルトンの深い音楽的秘密の井戸に酔わせる、胸が締め付けられるようなブルージーでほろ甘いコンテンポラリー・フォークの一大傑作アルバム。Brian Barrによるライナーノーツが付属し、彼女の友人や音楽協力者へのインタビュー・エッセイを収録。〈RTI〉での高品質プレス。豪華ゲートフォールド・ジャケット仕様。衝撃的なデビュー作の決定版として相応しいヴァージョンです。


各所で即完売となっていた人気盤です、お見逃しなく!ニューエイジ・ファンにも推薦!サックス、チェロ、ピアノ、フルートを中心に繰り広げられる親密で優美なコスミッシェ・アンビエント・ジャズ・サウンド。ポートランドの「偉大なブラックミュージック」の最高の実践者、The Cosmic Tones Research Trioが、母なる地球へと捧げる音楽『All is Sound』が〈Mississippi Records〉よりアナログで登場。ゴスペルやブルースのルーツやスピリチュアル・ジャズの要素も内包した、癒しと瞑想に捧げる、真摯で宇宙的なレコードに仕上がっています。

ジョン・コルトレーンがアトランティックに残した最後のアルバム『Olé Coltrane』。彼の音楽的転換点を示す重要作で、録音はインパルス移籍直後、名門ヴァン・ゲルダー・スタジオにて行われ、レギュラー・クインテットに加え、アフリカン・ブラス組からアート・デイヴィスやフレディ・ハバードらが参加。スペイン風味のミニマルで催眠的な演奏を軸に、ビバップからスピリチュアルな探求へと進むコルトレーンの次の時代の幕開けを示す一枚。


1988年から1994年にかけてのTappa Zukieによる代表的プロダクションをまとめた初のコンピレーション『Tappa Records Showcase』が登場。Horace AndyやJunior Ross、Prince Allaといったジャマイカの名シンガーたち、そしてSly & RobbieやClive Huntといった錚々たるプレイヤー陣を迎えた、黄金の10曲が高音質リマスターで初ヴァイナル化。若くしてトレンチタウンのサウンドシステム文化に魅せられ、ルードボーイの世界に飛び込んだTappaは、70年代には自らの〈Stars〉レーベルを拠点にプロデューサーとして頭角を現し、Roots期の名作を多数世に送り出すことになる。80年代半ば、ジャマイカの音楽がデジタル化し変化していく中で、彼が設立した〈Tappa Records〉では、時代のサウンドを取り込みながらも、あくまでルーツの精神を核に据えた“Digital Roots”という新たな地平を切り拓いた。このコンピはまさにその記録で、ラヴァーズロックからコンシャスなラスタ・チューンまで、80年代後半〜90年代初頭のジャマイカ音楽の転換点を、鮮やかにとらえたセレクション。現在のサウンドシステム・カルチャーにも通じる、タッパ・ズーキーの先見性と職人技が詰まった濃密なアーカイヴ。

ブラジル音楽とジャズが美しく溶け合う、ミルトン・ナシメントの国際デビュー作『Courage』。アレンジと指揮はエウミール・デオダート、鍵盤にハービー・ハンコック、ドラムにアイアート・モレイラなど、当時のジャズ・シーンの名手たちが揃って参加。ナシメントのヴォーカルは、土の匂いを感じさせるフォルクローレのようでありながらも、空を漂うように浮遊感に満ち、そこに重なる繊細なオーケストレーションと相まって、ソウルフルで夢見心地な音世界が広がる。ボサノヴァ以降のブラジル音楽の扉を開いた、静かな革新の名盤。


Slomoによる2005年のドゥーム・ドローンの金字塔『The Creep』が、20周年を迎えて初のアナログ・リイシュー。かつてJulian Copeのレーベル〈Fuck Off & Di〉から100枚限定でCD-Rリリースされ、瞬く間にカルト的評価を獲得したこの作品は、Holy McGrail(ギター)とHoward Marsden(シンセ)によるデュオが、たまたま録音したとされる偶発性に満ちた1曲61分の音の儀式。英国の地下霊廟ボリー・フォグーをイメージソースに、死と再生の気配をたたえた漆黒のアンビエンスを滲ませ、重低音の持続、サイケデリックな湿り気、時に野性味ある英国的な湿地帯のイメージを喚起しつつ、EnoやCOIL、Sunn O)))とも通じる深淵な音世界を展開する。スロウモーな時間感覚と地を這うような音圧は、聴く者を内なる風景へと沈め、やがて儀式的な覚醒へと導く。今回〈Ideologic Organ〉からの再発にあたり、Rashad Beckerがリマスターを手がけ、理想的なヴァイナルとして結実した。ドゥームの物理的重さとアンビエントの霊的静けさが交差する、唯一無二の音響体験。アンビエント、ドローン、ドゥーム、スピリチュアル・サイケデリアの交差点に咲いた奇跡のような一枚。