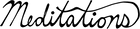MUSIC
6359 products

ライブ・アルバムの比喩を弄びながら、これまでにないほどカルテットの活気に満ちたエネルギーを捉えたレコーディングのコレクション。〈Ehse Records〉や〈Northern Spy〉といった各地の名門レーベルから秀逸な作品を送り出す実験的バンドHorse Lords。現行エクスペリメンタル・シーンを牽引するブルックリンの名門〈Rvng Intl.〉から最新ライブ・アルバムを発表。過去6年間に行われた様々なライブ・パフォーマンスを再編曲したものとなっており、2020年の地元ボルチモアでのライブや、2018年の〈Moers Festival〉でのパフォーマンスなどから構成される、ライブ・ショーの熱狂と激しさを備えた挑発的で完全なジャムを堪能できる一枚となっています。

Pitchforkでは8.4点、「BEST NEW REISSUE」のスコアを獲得!チェロ奏者、現代音楽の作曲家、ディスコミュージックへの傾倒と様々な顔を持つArthur Russell。そのパートナーであったトム・リーとオーディカ・レコードのスティーヴ・ナットソンによって発掘された彼の70年代初頭の未発表音源シリーズ、ラッセル・アーカイヴの最新アルバムが登場です!本作では、Rhys Chatham、Peter Gordon、Jon Gibson、David Van Tieghem、Henry Flyntといったミュージシャンもコラボレーション。収録された音源のうち、いくつかはデモとして録音されていたものや、コロンビア・レコードの伝説的プロデューサーである、ジョン・ハモンドのもとで行われたレコーディングも収録。



Gilles PetersonやAlice Russellからも支持され、世界的な注目を集めるテルアビブのトランペッターSefi Zislingによるサード・アルバム『The Librarian』が〈Tru Thoughts〉から発売!クラシックの要素に、サイケデリック・ファンク、ソウル、スピリチュアル・ジャズをブレンドした本作は、彼が親愛なるものすべてに捧げる作品であり、自身が受けた音楽的影響から、彼の妻や友人、そして彼に感銘を与えたパレスチナ人Eyadに敬意を表している。
「このタイトルを選んだのは、私がこの作品の司書(Librarian)だから。私は司書のように音楽を記憶し、頭の中でカタログ化し、それを堪能している。つまり、この作品には、私が愛聴している音楽ライブラリーから参照した「絵葉書」が散りばめられているんだよ。」
Bennie Maupinの『The Jewel in Lotus』から着想を得たタイトル曲「The Librarian」から、Sefiの妻を表現した「豊かで、力強く、生き生きとした」インストゥルメンタルの「Layla」、そして、警察の発砲により悲劇的な死を遂げた自閉症パレスチナ人に捧げる「Song for Eyad」まで、Sefi Zislingの作曲家、演奏家としての進化が凝縮された全6曲!



モールソフトやユートピアン・ヴァーチャルといったサブジャンルを横断しながらヴェイパーウェイヴの発展を支えてきたニューヨークのレジェンド식료품groceriesによる2015年のアルバム『HOUSEWARES』が、現行ヴェイパーウェイヴにおける重要レーベル〈Geometric Lullaby〉よりリマスタリング仕様でアナログ化!ヴェイパー全盛期に残された隠れたクラシックの一つといえる作品と言える本作は、独特のメロウネスとシュルレアリスティックな雰囲気、電脳的サイケデリア、ノスタルジックな淡い感傷が美しくレイヤーされ、ほろ苦く、ミステリアスな世界観を演出した、よりコンセプチュアルな仕上がりのモールソフト作品。


UKライブラリー・レジェンドBrian Bennettのコズミック・ディスコ・クラシックに、アルゼンチンから日本の環境音楽への回答と言える人気ユニット=The Kyoto Connection、世界各地のオブスキュア・ディスコ、ブギーに至るまで、審美眼を感じる数々の卓越したリリースで知られる豪州の名門発掘レーベル〈Isle Of Jura〉からは、2022年に始動したインスト・ダブを集めたミニ・コンピレーション・シリーズ『Instrumental Dubs』の第一弾がスリーヴを新装した2024年エディションで再登場。マーヴィン・ゲイの名曲をアイランド・ディスコでカバーしたGlen Adams & Finesseでオープンを飾り、続いてA2ではTippa Irieの”Panic”の超レアなUKブギー/ブリット・ファンク・ミックスを披露、ラストは華麗にLa Palace De Beauteの”Sin”のJura Soundsystemによるダビー・エディットでボーカルを引っ込め、ディレイを強めて締めくくる秀逸作品!プロト・ヴェイパーウェイヴ的な視点からもユニークな内容です!










Erik Satie, Debussyなどの西洋音楽のエッセンスとエチオピア教会音楽の悠久の歴史が物語る神聖美が邂逅し、アフリカの約束の大地の上にて魂の脈打つ鼓動と瞑想の響きが混ざり合った孤高の音楽であり、女性版Dollar Brandとも言える感動的なモダン・クラシカル。ピアノのみの純粋な音楽性とレトロな音質がたまりません。スピリチュアルな音源がお好きな方は当然マストですが、幅広い音楽ファンへとお薦めしたい果てなき霊性漂うマスターピース。




(数量限定クリア・ヴァイナル/日本語帯付き/日本限定発売)。サンダーキャット、ベニー・シングス、ジェイペグマフィア他豪華ゲスト参加!超人気ビートメイカー、ケニー・ビーツ待望のソロ・アルバム!!
サンダーキャット、ヴィンス・ステイプルス、ジェイペグマフィア、デンゼル・カリー、リコ・ナスティ、さらにはマック・デマルコからベニー・シングスまで共演およびプロデュースやコラボレーションを行うほか、YouTubeやDiscordを駆使した発信力でカリスマ的人気を誇るビートメイカー/プロデューサーのケニー・ビーツが自身初となるソロ・アルバム『LOUIE』をリリース!!
世界がパンデミックに一瞬にして覆われた時、人気ロック・バンドのアイドルズのプロデュースを行うためUKに滞在していたケニーは愛する父親が膵臓がんと診断されたとの連絡を受け取る。
幼き日に父が作ってくれたシャーデーやウィリー・ネルソン、ドクター・ドレーなどが入ったミックステープを聞き返したケニーは様々な感情が甦り、気づけば父親に贈り物をしようと決意した。
決してソロ・アルバムは作らないと公言してきたが、結果としてここに感動的なソウル・オデッセイのループが胸を打つ17のビートが完成。
なお本作にはサンダーキャット、コリー・ヘンリー、ベニー・シングス、ジェイペグマフィア、ピンク・シーフ、マック・デマルコ、オマー・アポロ、スロウタイ、ディージョン、レミ・ウルフ、ヴィンス・ステイプルズ、マシュー・タヴァレス、イーゴンといった錚々たる盟友たちがレコーディングに参加している。

映画『アキラ』と日本の風景からインスパイアされたコズミックワールド、即完売したLPの再プレス盤が登場です
フランスのマルチインストゥルメンタリストであるパスカル・ビドーは、ガムランとゴングをエレクトロニカとジャズに融合させたアーティストで、彼ががインドネシアを訪れた際に伝統的なガムランとゴングの音楽に没頭したことが発端で制作された作品です。テーマ、モチーフ、メロディーの多くはガムランで使われる重要な調律法の一つである「スレンドロ」音階が使われ、シンプルなサックス のライン、シンセ、ブラス、ストリングスが徐々に変化して独特のコズミックな世界観を作り上げています。アルバムの中心である’Neo Tokyo’は大友克洋監督の「AKIRA」からインスピレーションを受けたもので広大な未来 の大都市を舞台にした目 まぐるしい芸術作品を想起させます。一方”Yurikamome”はビドーが日本への憧れを抱き日本の 風景や都市をドライブしているYoutubeのビデオを見てインスピレーションを受けた想像上のサウンドトラック。今作には Daniel Brandtを始めBrandt Brauer Frick(ドラムス/電子パーカッション)、Florian Juncker(トロンボーン)、Ruth Velten(サックス)が参加。


『Rain Before Seven...』には楽観主義が息づいています。それは自慢げで自信過剰なものではなく、イギリスの国民性を表した軽薄で自虐的な楽観主義です。彼らはたとえあらゆる予兆が無かったとしても物事はうまくいくという確信のもとに動いているのです。
タイトルは韻を踏んだ予言とも言える古い天気予報のことわざに由来しています。ー11時前には晴れるー それは科学とは関係なくハッピーエンドを意味する言葉。アーサー・ジェフス曰く「それまで聞いたことが無かったけどある本でその言葉を見つけたんだ。かすかに楽観的なニュアンスがあってとても好きな言葉だよ。最近は使われなくなったけど大西洋から入ってくるイギリスの気象パターンを表現しているんだ。」
モリコーネを意識したオープニング"Welcome to London”から始まり"Goldfinch Yodel"まで映画を見ているような余韻に浸れます。そして常にエキゾチックなリズムの高揚感を感じながらもそこには悲壮感が漂っているのです。2011年の省略記号で締めくくられたアルバムタイトル「A Matter of Life...」にちなんだタイトル名には遊び心を感じます。そのペンギン・カフェとしてのデビューは父であるサイモン・ジェフスが率いた伝説のペンギン・カフェ・オーケストラとアーサーが率いる愛すべき子孫との架け橋となっているのです。
「スタイル的には遊び心のあるリズムや楽器使いに戻ることができてとても満足している」と語る若きジェフスは12年前のデビュー作を念頭に置いて新作を制作しました。「当初あったテクスチャーを今は使わなくなっていることに気付いたんだ。それらの要素は父の初期の作品に沢山あったんです。だからウクレレ、クアトロ、メロディカなどの音楽的にも地理的にもまったく異なる地域のテクスチャーやバラフォンが多く入っているんだ。」
『Rain Before Seven...』を聴けばそのテーマが単なる天気予報では無いことが分かるだろう。ある意味この作品は危険が去って行くのを橋の下で待ちながら書き留めた音楽の日記と言えるでしょう。彼は私たちと同じように2020年に自分が監禁されていることに気づきました。COVID-19の最中、最初のヨーロッパの目的地はイタリア。彼と家族は当時トスカーナの修道院を改造した建物に滞在していました。この修道院は彼の母親で有名な石像彫刻家であるエミリー・ヤングと12年ほど前に購入した建物です。オリーブの木に囲まれた丘陵地に検疫で足止めを食らうには最高の場所でしたが、一家は世界の多くの人々と同じように切実な不安と不確実性に直面していたのです。
そのため今作にはこの時期の個人的な体験に関する楽曲が多く収録されています。”Galahad"は16歳で亡くなったアーサーの愛犬を讃えた楽曲で15/8拍子で書かれています。”Lamborghini 754"は彼が母親のために買った40年前のトラクターがスタジオからオリーブ畑を横断しているのが見えたことから名付けられました。自身で操縦出来る広大なスペースがあったことは、都市や町に住む何百万人もの人々が経験することの出来ない贅沢であり幸運でした。さらに都会で暮らす人々の苦悩は、アーサーの父親が描いたペンギン・カフェ・オーケストラが誕生するきっかけとなったビジョンと不気味に重なり合ったのです。
1972年父であるサイモン・ジェフズは南フランスで休暇を過ごしているときに不味い魚を食べた事が原因で幻覚を見るようになりました。 「ベッドに横たわると奇妙な幻覚が繰り返された」と彼は後に語っています。「目の前にはホテルか公団住宅のようなコンクリートの建物があり、それぞれの部屋は遠隔で絶えずチェックされていた。部屋には人が居るけどみんなが"うわのそら"なんだ……」「しかも全くの沈黙だった。まるでその場にいる全員が無力化され色も無く匿名にされたように。その光景は私にとって秩序ある荒廃を想像させた」こんな未来の予感を払拭してくれたのが"無意識になれる場所"自由気ままなペンギン・カフェだったのです。
アーサーによれば父であるサイモン・ジェフズのイメージは"少し風変わりな古美術的アプローチ"で音楽を組み立てて耳に優しい音を再構築する人”でした。これは戦後の文筆家たちによる真剣な反応があったミニマリズムの台頭と同時期だったのかもしれません。「しかし父はブーレーズもジョン・ケージも大好きでした」とアーサーは付け加えます。クラシック音楽がポップスや東アフリカのリズムと融合することはインターネット時代(そしてPCOが決して嫌がらなかった広告においても)にはそれほど特別な事ではありませんが、1970年代の当時彼らはブライアン・イーノのレーベルObscureに所属して自分達がやっていることの難解さを実感していたのです。ペンギン・カフェ・オーケストラは長い間ルシェルシュ(フランス語で精選された物の意味)のままではいられなかったのです。
「父の斬新なアプローチは面白くて奇妙なアイデアを取り入れて奇妙なことをすることだったと思います。しかし常に美しく感情移入できるサウンドにすることを意識していました」とアーサーは語ります。その精神はペンギン・カフェにも受け継がれています。「父の音楽を演奏する一方で、同じ世界で新しい音楽を演奏するのです。つまり原点に立ち返りスラッシュ・メタルの領域に踏み込まないように気を配るのが私の役目です」
しかし、共同プロデューサーのRobert Rathsに後押しされ『Rain Before Seven…』のリズム要素はかつてないほど前面に押し出され、エレクトロニカを彷彿とさせる楽曲もあります。例えば"Find Your Feet”は単純にパルス音だけで構築された楽曲ではありません。Tom Chichester-Clarkがミックスしたこの曲は、アーサーが「エレクトロニックに近い感覚」と表現するように彼らの音楽に新たな融合をもたらしています。そして彼は興奮気味にこう付け加えます、「過去3枚のレコードではあまりやらなかったような楽しい要素がここにあるんだ。」アンビエントのゴッドファーザーであるハロルド・バッドに捧げた"In Re Budd”はこの曲を書いた日に彼が亡くなっていたことに気づき、シンコペーションが巧妙なアレンジを加える事で追悼したのです。アップライトピアノで演奏し音の跳ねを強調するために”プリペアド"フェルトを使用しました。アフロ・キューバン・カフェのような雰囲気があるこの楽曲はバッドの異質さをアピール出来たと彼は感じています。
そして"Welcome to London"は世界が再び動き始め人々が飛行機に乗れるようになった事からその名が付きました。久しぶりに故郷に降り立った彼はヒースロー空港からタクシーで西ロンドンに向かい、控えめな薄明かりの背景をバックに007の映画を想起させる雰囲気に心を打たれたのです。楽観主義がそこにあり少し辛辣な皮肉もあるのかもしれません。「ロバート・ラス(Erased Tapesのオーナー)は今作に興味深いニュアンスを加えてくれました。多くのロンドン市民はもともとロンドン出身ではないのです。ロンドンにはよそ者としてやって来て、まだ自分の仲間を見つけられないうちに強盗に襲われる…そうなると"Welcome to London"はより皮肉な響きを帯びてくるんだ。」

サンダーキャット、ベニー・シングス、ジェイペグマフィア他豪華ゲスト参加!超人気ビートメイカー、ケニー・ビーツ待望のソロ・アルバム!!
サンダーキャット、ヴィンス・ステイプルス、ジェイペグマフィア、デンゼル・カリー、リコ・ナスティ、さらにはマック・デマルコからベニー・シングスまで共演およびプロデュースやコラボレーションを行うほか、YouTubeやDiscordを駆使した発信力でカリスマ的人気を誇るビートメイカー/プロデューサーのケニー・ビーツが自身初となるソロ・アルバム『LOUIE』をリリース!!
世界がパンデミックに一瞬にして覆われた時、人気ロック・バンドのアイドルズのプロデュースを行うためUKに滞在していたケニーは愛する父親が膵臓がんと診断されたとの連絡を受け取る。
幼き日に父が作ってくれたシャーデーやウィリー・ネルソン、ドクター・ドレーなどが入ったミックステープを聞き返したケニーは様々な感情が甦り、気づけば父親に贈り物をしようと決意した。
決してソロ・アルバムは作らないと公言してきたが、結果としてここに感動的なソウル・オデッセイのループが胸を打つ17のビートが完成。
なお本作にはサンダーキャット、コリー・ヘンリー、ベニー・シングス、ジェイペグマフィア、ピンク・シーフ、マック・デマルコ、オマー・アポロ、スロウタイ、ディージョン、レミ・ウルフ、ヴィンス・ステイプルズ、マシュー・タヴァレス、イーゴンといった錚々たる盟友たちがレコーディングに参加している。







近年のMOCKY作品には欠かせない、ミゲル・アトウッド・ファーガソン、ジョーイ・ドォシク(ここでは鍵盤ではなく管楽器担当!)、ニア・アンドリューズに加え、鍵盤奏者、デロン・ジョンソン(マイルス・デイヴィスの "Doo Bop")、管楽器奏者、ランダル・フィッシャー(Kadhja Bonet、デクスター・ストーリー ほか)ベイシスト、ブランドン・ユージン・オーウェンズ(ケンドリック・ラマー、ロバート・グラスパー、ギャビー・ヘルナンデス、テラス・マーティン、ミア・ドイ・トッドほか)日本では数々の作品を通じてお馴染みであろう、マーク・ド・クライブ・ロウなどLAをべースに立派なキャリアを築いているミュージシャンたちが初参加していることも大きな特徴。
どこか2009年の4th アルバム「SASKAMODIE」を思い起こさせるこの新作。パリで録音されたあのアルバムに流れる時間が夜だとすればこの新作はLAの午後の陽光に微睡む時間のような。今もFRESHな1971年のスティーヴ・キューン、1973年のクインシー・ジョーンズ、1976年のRoy Ayers Ubiquity、70年代中頃のMizell Brthersの傑作群を聴く時間のような音の快楽に溺れること請け合い。やけに艶やか。』